公開日 2023/08/15
【医師解説】1ヶ月健診でわかること|内容・費用・持ち物・受診時の注意点について

目次
この記事の監修者

さの赤ちゃんこどもクリニック 院長
佐野 博之 先生
Q.1ヶ月健診とはどのようなものでしょうか?
A.生後1ヶ月を迎えた赤ちゃんの成長と発達を評価する重要な健康診断です。この健診では、医師や保健師が赤ちゃんの身体的な発育や健康状態をチェックします。母乳やミルクの授乳方法、赤ちゃんの睡眠パターン、母親の体調などが確認され、必要なアドバイスを提供します。赤ちゃんの健康を把握し、早期に問題を発見して適切な対処を行うために非常に重要な健康診査(健診)です。
Q.1ヶ月健診では何を診るのでしょうか?
A.大きく3つあります。体重がきちんと増えているか、原始反射があるか、そして先天性の病気がないかどうかです。健診の流れとしては、問診、身体測定、医師による診察、ビタミンK2シロップの投与、生後すぐに受けたスクリーニング検査の結果説明、子育てに関する相談などを行います。診察では、視診や聴診、触診のほか、音への反応や、舌や喉に異常がないかなどを見たりします。細かい内容は医療機関によって異なることもあります。
身体測定
身体測定では、赤ちゃんの身長、体重、頭囲などを計測します。計測した結果は、母子健康手帳に記載されます。
参考:生後1ヶ月の赤ちゃんの成長の様子
個人差はありますが、出生時から1ヶ月で身長が約5cm、体重が約1kg増えていれば順調に発育しているといえます。
生後1ヶ月の身長・体重目安
■男の子:身長50.9~59.6cm / 体重3.5~6.0kg
■女の子:身長50.0~58.4cm / 体重3.4~5.5kg
参考:厚生労働省 平成22年乳幼児身体発育調査報告書
生後1ヶ月の赤ちゃん|ミルク量・授乳間隔・睡眠時間の目安につて
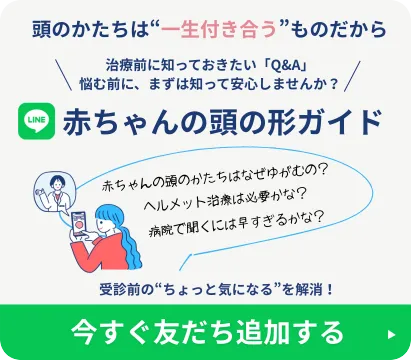
授乳量・間隔の目安
母乳に関しては、赤ちゃんが欲しがるときに、欲しがるだけあげれば問題ありません。1日8~10回ほどが目安となりますが、それ以上になることもあります。体重の増え方が1日平均20g未満の場合は、小児科で相談してください。生後2~3ヶ月になれば、授乳間隔が安定し、回数も徐々に減ってきます。しかし、赤ちゃんによって個人差が激しく、なかなか授乳が安定しない赤ちゃんもいるので、不安がある場合は医師に相談してください。
赤ちゃんの吐き戻しはいつまで続く?原因や対処法対処法について
睡眠量の目安
生後1ヶ月ほど経つと、寝てばかりの赤ちゃんも、徐々に長い時間起きていられるようになります。平均的には3~4時間おきに起きるようになりますが、個人差が大きく、長く寝る子もいれば細切れ睡眠の子もいます。
新生児(赤ちゃん)が寝ないときは?昼間や夜中に寝ないときの原因や寝かしつけのポイント
原始反射とは
胎児期や新生児期から幼児期にかけて、生まれつき備わっている反射的な動作のことです。神経系の発達に伴って現れ、一時的に存在し、後に発達段階に合わせて消失していく特徴があります。原始反射は生命の維持や運動の発達に関与しており、特定の刺激に対して自動的に生じる反応です。これらの反射は、新生児の適応能力や生存に必要な動作をサポートする役割を果たしていますが、徐々に姿勢反射や後天的な反射に取って代わられることで、適切な運動の制御が可能になります。
以下のような原始反射をチェックします。
バビンスキー反射って何?赤ちゃんの発達チェックポイントについて
【把握(はあく)反射】
手のひらに触れられると自動的に手を握る反射的な動作のこと。この反射は、赤ちゃんが生まれつき持つ反応の一つです。
【モロー反射】
予期せずに刺激を受けると、腕を広げた後に突然抱き寄せるような動作を行う反射的な動作です。この反射は、生後数週間から3か月程度までの間に見られます。
モロー反射はいつからいつまで?激しいときの対処法3つと動きが似ている疾患を解説
【吸啜(きゅうてつ)反射】
新生児が口に何かを触れると自動的に吸うような反射的な動作のことです。この反射は、生まれつき持っている原始的な反応の一つであり、赤ちゃんの生存と栄養摂取をサポートする役割を果たしています。
【非対称性緊張性頸反射(ひたいしょうせいきんちょうせいけいはんしゃ)】
新生児や乳児期の赤ちゃんが頭を一方向に傾けると、同じ方向の手足が伸び、反対側の手足が曲がるような反射的な動作のことです。
医師による診察
視診、聴診、触診をして赤ちゃんの全身の状態をチェックを通して、赤ちゃんが健康に育っているかを調べます。心雑音や湿疹などの確認、へそに異常が生じていないか、音や光への反応はどうか、手足をよく動かすかなど運動発達の観察なども行います。
乳児湿疹ができる原因は?アトピー性皮膚炎との違いや対策について
ハンドリガードとは?ハンドリガードの理由や見られる時期、発達との関係について
クーイングとは?喃語とは?始まる時期や役割、赤ちゃんの言葉の発達について解説
ビタミンK2シロップの投与
赤ちゃんに起こりやすい出血を防ぐため、ビタミンKを含むビタミンK2シロップを投与します。計3回内服させる方法(出生後、生後1週間、生後1ヶ月)と、生後3ヶ月まで毎週1回投与する方法があります。
生後間もない時期に受けたスクリーニング検査の結果説明
新生児先天性代謝異常等検査(新生児マススクリーニング)や、新生児聴覚検査(新生児聴覚スクリーニング)などの検査を受けている場合は結果説明などがあります。
子育てに関する相談
授乳や夜泣きへの対応、子育てに関する不安などを相談することができます。また、産後の身体の回復がままならず、睡眠が不足しがちで、気分が落ち込みやすい時期でもあります。
赤ちゃんの夜泣きはいつからいつまで?原因と乗り越えるための対策を解説
黄昏泣き(コリック)はいつからいつまで続く?5つの対処方法と対策グッズを紹介
参考:
Zafeiriou, Dimitrios I. "Primitive reflexes and postural reactions in the neurodevelopmental examination." Pediatric neurology 31.1 (2004): 1-8.

Q.必要な持ち物を教えてください。
A.基本的に、必要なものは各医療機関から伝えられます。一般的には以下のものを持ってくるように指示されます。
<健診を受けるために必要なもの>
- 母子健康手帳
- 健康保険証
- 乳幼児医療費受給者証(子ども医療費受給者証)
- 乳幼児健康診査受診票(自治体が1か月健診を公費負担の対象としている場合のみ)
- 診察券
- 問診票(事前に渡されている場合のみ)
- 健診の費用
<赤ちゃんに必要なもの>
- 着替え 1~2セット
- 肌着1枚+ベビー服1枚で1セット
- おむつ 3~5枚
- おしりふき
- ビニール袋2~3枚
- ガーゼ 1~2枚
- おくるみor大きめのバスタオル
<授乳時に必要なもの>
- 授乳ケープ
- 哺乳びん
- 授乳用ミルク
- 調乳用のお湯
Q.健診に費用はかかるのでしょうか?
A.赤ちゃんの1ヶ月健診にかかる費用は、一般的に保険診療外のため自己負担となります。自治体によっては、受診した分の費用を助成する制度を設けていることがあります。費用は医療機関によって異なりますが、5000円~1万円ほどがおおよその目安になります。
薬の処方など保険診療を受けた場合は健診とは別に費用が発生することがありますので、保険証や乳幼児医療費受給者証がある場合は必ず持参してください。公費負担の対象となる自治体に居住していて、里帰り出産などで居住する地域以外の医療機関で健診を受けた場合は、後日、居住する自治体へ申請すると払い戻しを受けることができます。
健診の費用について、気になることがある場合は、健診を受ける医療機関へ問い合わせましょう。また、自治体による公費負担の制度については、居住する自治体の公式ホームページ等で確認してみてください。
Q.赤ちゃんの服装はどのようなものが良いでしょうか?
A.診察や測定の際にはおむつ1枚になるので、着脱しやすい前開きタイプがおすすめです。着せる枚数は、肌着1枚+ベビー服1枚で、普段着ている服で問題ありません。また、おくるみが1枚あると、保温したり、日除けにもなるので便利です。
赤ちゃん(新生児)との外出はいつから?外出時間の目安や持ち物リストを紹介
Q.健診項目以外で注意した方がよいことはありますか?
A.赤ちゃんが同じ方向を向いて寝ることで、頭の形がゆがんでしまうことがあります。生後1ヶ月は、頭のゆがみの予防や、ゆがみの改善がしやすい時期です。体位変換やタミータイム(うつぶせで遊ばせる時間をとる)でゆがみの予防や改善を試みてください。
赤ちゃんの頭の形のゆがみは放っておいても大丈夫?ゆがみの原因・予防・対策について
①定期的に体の向きを変える(体位変換)
A.ベッドやベビーカーで寝ている方向や、授乳の向き、抱っこの向き等、バランスよく体の方向を変えてあげることで、赤ちゃんの頭の圧力が均等に分散され、頭のゆがみを防ぐことができます。
②うつぶせで遊ばせる時間を取る(タミータイム)
A.うつぶせで遊ばせることによって、首や背中の筋肉を鍛えると同時に頭の圧力を軽減し、頭形変形の予防に役立ちます。1日2~4回程度、最初は数分だけでも大丈夫なので、少しずつ時間を増やし、トータル1日60分程度を目安に実施すると良いと思います。うつ伏せのまま寝かせることは、乳児突然死症候群(SIDS)の危険性が高まりますので、必ず赤ちゃんが起きている時に行い、目を離さないようにしましょう。
タミータイム(うつぶせ遊び)とは?6つの効果と月齢別のやり方、注意点について解説
ベビーマッサージとは?6つの効果とやり方、注意点についても解説
Q.1ヶ月健診を終えるとどのようなことができるのでしょうか?
A.沐浴を卒業して大人と一緒のお風呂に入れるようになります。散歩や買い物など、外出する機会を増やす親子も増えてきます。赤ちゃんは抵抗力が弱いので、時間帯を選び、人混みを避けて、親子で外出することに少しずつ慣れて行くのも良いでしょう。乳児健診は、普段の生活では気づいていない成長や発達の変化を見つける目的もありますので、適切な時期にしっかり受けるようにしましょう。
3,4ヶ月健診は何をチェックする?内容や費用、注意点について
乳幼児健診はいつ受ける?乳児健診の目的や健診のスケジュールについて





