公開日 2025/08/12
【医師解説】高齢出産は何歳から?35歳を境に変わるリスクと対策

目次
この記事の監修者
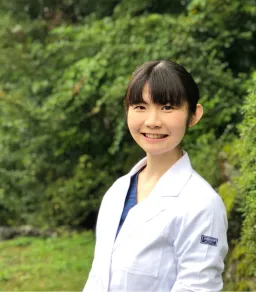
久保田産婦人科病院
西野 枝里菜 先生
35歳以上で妊娠・出産を考えるパパ・ママの中には、「高齢出産は何歳から?」「どんなリスクがあるの?」と不安を抱える方も多いでしょう。晩婚化が進む現代では高齢出産は珍しくなく、医療技術の進歩により安全に出産される方も増えています。
本記事では、産婦人科医の立場から、高齢出産の定義や具体的なリスク、そして安全な妊娠・出産のための対策について詳しく解説します。
ブライダルチェックとは?検査内容・費用・受けられる場所・ペアで受けるメリットまで
高齢出産は何歳から?35歳以上が区切りとされる理由

高齢出産は日本では35歳以上の初産を指します。晩婚化やキャリア志向の影響で、高齢出産は増加傾向にあります。近年の医療技術の進歩により、高齢でも安全に出産できる可能性が高まっています。
ぜ35歳以上が「高齢出産」とされるの?医学的について
高齢出産の定義は、日本では35歳以上で初めて出産する場合を指します。これは日本産科婦人科学会によって定められた基準です。一方、国際的には初産婦の場合は35歳以上、経産婦の場合は40歳以上とする場合もあります。
この35歳という基準は、統計的に妊娠や出産に関するリスクが明らかに上昇し始める年齢として設定されています。ただし、これは統計上の目安であり、35歳を境に急激にリスクが高まるわけではありません。個人差も大きく、35歳以上でも健康な赤ちゃんを出産される方は数多くいらっしゃいます。
第二子以降を高齢で出産する場合は「高齢経産婦」と呼ばれ、初産とは異なるリスクや注意点があります。高齢経産婦の場合、前回の出産からの期間や既往歴なども重要な要素となります。
どうして高齢出産は増えているの?社会背景を解説
近年、高齢出産は大幅に増加しています。厚生労働省の統計によると、35歳以上で初産を迎える女性の割合は過去20年間で約2倍に増加しました。この背景には、晩婚化の進行、女性の社会進出、経済的な理由などが挙げられます。
キャリアを重視する女性が増えたことで、結婚や出産のタイミングが遅くなる傾向があります。また、経済的な安定を求めて出産を先延ばしにするケースも少なくありません。これらの社会的要因により、出産年齢の上昇が続いています。
一方で、不妊治療技術の進歩により、以前は困難とされていた年齢での妊娠・出産が可能になっています。体外受精をはじめとする生殖補助医療の発展が、高齢出産の選択肢を広げているのも現状です。
統計からわかる高齢出産とは?35歳以上での割合
2022年の厚生労働省出生統計によると、35歳以上で第一子を出産した女性の割合は約30%に達しています。、40歳以上でも6%を超えています。特に都市部では、この割合がさらに高くなる傾向があります。
年齢別の出生率を見ると、20代後半から30代前半がピークとなっていますが、35歳以降も一定の出生率を保っています。40歳以上での出産も年々増加しており、医療技術の進歩が高齢出産を支えていることがわかります。
また、初産年齢の平均は年々上昇しており、現在では30歳を超えています。これは先進国共通の傾向で、日本だけでなく欧米諸国でも同様の変化が見られます。
母親の年齢 | 出生数(2022年) | 割合 |
|---|---|---|
〜19歳 | 4,558人 | 0.59% |
20〜24歳 | 52,850人 | 6.86% |
25〜29歳 | 202,505人 | 26.27% |
30〜34歳 | 279,517人 | 36.27% |
35〜39歳 | 183,327人 | 23.79% |
40〜44歳 | 46,338人 | 6.01% |
45〜49歳 | 1,600人 | 0.21% |
50歳以上 | 58人 | 0.01% |
出典:厚生労働省「第4表 母の年齢(5歳階級)・ 出生順位別にみた出生数」より
高齢出産は何が心配?知っておきたい主なリスク

高齢妊娠では流産率や胎児の染色体異常のリスクが上昇します。妊娠高血圧症候群などの合併症にも注意が必要です。正しい知識を持つことで、リスクを最小限に抑えられます。
流産率は何歳から上がる?年齢別の変化
高齢出産において最も注意すべきリスクの一つが流産率の上昇です。流産率は年齢別に大きく異なり、20代後半から30代前半では約10-15%程度ですが、35歳以降は明らかに上昇します。
具体的な数値を見ると、35-39歳では約20-25%、40-44歳では約33-40%程度まで上昇するとされています。これは主に卵子の老化による染色体異常の増加が原因です。ただし、これらの数値は統計的な平均であり、個人の健康状態や生活習慣によって大きく左右されます。
流産の多くは妊娠12週以前の早期流産で、その約80%が胎児の染色体異常によるものです。年齢が上がるほど卵子の質が低下し、染色体異常が起こりやすくなるため、流産率も上昇するのです。
切迫流産の症状・原因・治療法|流産・切迫早産との違いについて
ダウン症など染色体異常のリスクは何歳から増える?
高齢出産では、胎児の染色体異常、特にダウン症の発生率が上昇します。ダウン症の発生率は母体年齢と密接に関連しており、20歳では約1/1500、30歳では約1/900、35歳では約1/350、40歳では約1/100、45歳では約1/30まで上昇します。
このような数値を見ると不安になるかもしれませんが、逆に考えると、45歳でも約97%の確率で染色体異常のない赤ちゃんが生まれるということでもあります。また、現在では出生前診断の技術が発達しており、早期に染色体異常を検出することが可能になっています。
染色体異常のリスクは母体年齢だけでなく、男性側の年齢(高齢父親)も関係することがわかってきました。男性の年齢が上がると精子のDNA損傷が増加し、一部の遺伝性疾患のリスクが微増することが報告されています。
35歳以上で注意したい妊娠合併症のリスク
高齢妊娠では、妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病、前置胎盤などの合併症のリスクが上昇します。これらの合併症は母体と胎児の両方に影響を与える可能性があり、適切な管理が必要です。
妊娠高血圧症候群は高齢妊娠で最も注意すべき合併症の一つで、35歳以上では20代の約2-3倍のリスクがあります。重症化すると子癇や胎盤早期剥離などの重篤な合併症を引き起こす可能性があります。また、妊娠糖尿病も高齢妊娠では発症リスクが高く、血糖値の管理が重要になります。
これらの合併症のリスクを最小限に抑えるためには、妊娠前からの健康管理と、妊娠中の定期的な検査による早期発見・早期治療が欠かせません。
妊娠超初期~妊娠初期のおりものの症状とは?生理前と何が違う?知っておきたい量や色の特徴と対策
高齢出産のリスクを減らすには?今からできる具体的な対策
妊娠前からの健康管理や生活習慣の見直しが大切です。専門医との連携や定期検査でリスクを早期発見しましょう。必要に応じて出生前診断も検討できます。
妊娠前から始めたい健康管理と生活習慣の見直し
高齢出産のリスクを減らすためには、妊娠前からの健康管理が極めて重要です。まずは、基本的な生活習慣の見直しから始めましょう。バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠、禁煙・禁酒などが基本となります。
特に葉酸の摂取は、胎児の神経管閉鎖障害を予防するために重要です。妊娠を計画している段階から、1日400μgの葉酸サプリメントの摂取が推奨されています。また、肥満や痩せすぎも妊娠に悪影響を与えるため、適正体重の維持が大切です。
持病がある場合は、妊娠前に主治医と相談し、薬の調整や治療方針の見直しを行うことが必要です。高血圧、糖尿病、甲状腺疾患などは妊娠に影響を与える可能性があるため、事前のコントロールが重要になります。
妊娠中に食べていいもの・避けたいものは?つわり中でも食べやすいおすすめ食材
高齢出産では健診や専門医のサポートが重要
高齢出産では、通常の妊婦健診に加えて、より頻繁な検査や特別な検査が必要になる場合があります。妊娠初期から産婦人科医との密な連携を保ち、個々の状況に応じた管理を受けることが大切です。
胎児の発育状況をより詳しく確認するため、エコー検査の頻度が増えることもあります。また、妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病の早期発見のため、血圧測定や血糖値検査も頻繁に行われます。
必要に応じて、母体胎児医学の専門医への紹介や、高次医療機関での管理が推奨される場合もあります。リスクの程度に応じて、適切な医療機関で管理を受けることが、安全な出産につながります。
出生前診断は受けるべき?検査方法と特徴を解説
高齢出産では、胎児の染色体異常のリスクが上昇するため、出生前診断について検討される方が多くなります。出生前診断には、からだへの負担が少ないとされる非侵襲的な検査から確定診断まで、様々な選択肢があります。
まず、妊娠初期に行われる母体血清マーカー検査やNIPT(非侵襲的出生前遺伝学的検査)があります。これらは採血のみで行える検査で、胎児への直接的なリスクはありません。NIPTは特に精度が高く、35歳以上の妊婦に推奨されることが多い検査です。
確定診断を希望する場合は、羊水検査や絨毛検査があります。これらは侵襲的検査で、わずかながら流産のリスクがありますが、染色体異常の有無を確実に診断できます。検査を受けるかどうかは、夫婦でよく話し合って決めることが大切です。
腹部のエコー検査でわかることは?エコー写真の見方や保存方法まで
高齢出産における不妊治療の現状について
体外受精などの不妊治療は年齢によって成功率が変わります。35歳以上は早めの治療開始が推奨されます。男性側の年齢や生活習慣も妊娠に影響することがあります。
体外受精の成功率は何歳から下がる?年齢別データ
高齢出産を考える際、不妊治療、特に体外受精について知っておくことは重要です。体外受精の妊娠率は年齢別に大きく異なり、母体年齢が上がるほど妊娠成功率は低下します。30歳未満では約40-50%の妊娠率がありますが、35歳では約30-40%、40歳では約20-25%、42歳以上では約10%以下まで低下します。
この妊娠成功率の低下は、主に卵子の老化による質の低下が原因です。年齢が上がると、正常な胚の発生率が低下し、着床率も下がります。また、流産率も上昇するため、生産率はさらに低くなります。
しかし、医療技術の進歩により、胚の選別技術や培養技術が向上し、従来よりも高い成功率を期待できるようになっています。個人差も大きいため、年齢だけでなく、卵巣機能や子宮の状態なども総合的に評価することが重要です。
不妊治療はいつから始めるべき?
高齢での妊娠を希望する場合、不妊治療を開始するタイミングは重要な要素です。一般的に、35歳未満では1年間の妊娠の試みの後、35歳以上では6ヶ月間の試みの後に不妊治療を検討することが推奨されています。
年齢が上がるほど、時間的な余裕が少なくなるため、早期の相談と治療開始が重要になります。特に40歳以上では、より積極的な治療が必要になる場合が多く、体外受精を第一選択とすることもあります。
不妊治療には心身ともに負担がかかるため、夫婦でよく話し合い、専門医と相談して治療方針を決めることが大切です。また、治療期間の目安を設けることで、精神的な負担を軽減できる場合もあります。
男性の年齢も関係する?妊娠への影響
高齢出産を考える際、男性側の年齢も重要な要素です。男性の妊孕性は女性ほど急激には低下しませんが、年齢とともに精子の質は徐々に低下し、40歳以降では明らかな変化が見られます。
高齢の父親では、精子のDNA損傷率が上昇し、流産率の増加や一部の遺伝性疾患のリスクが微増することが報告されています。また、精子の運動性や濃度も年齢とともに低下し、自然妊娠率に影響を与える可能性があります。
男性側の妊孕性を改善するためには、女性と同様に健康的な生活習慣の維持が重要です。禁煙、適度な運動、バランスの取れた食事、ストレス管理などが精子の質の向上に役立ちます。
高齢出産後の育児で大切なこと
高齢出産後は体力面での負担を考慮し、無理せず回復を図りましょう。家族や地域のサポートを活用することも大切です。長期的な健康管理と心のケアも忘れないようにします。
産後の体力回復と無理をしない育児の工夫
高齢出産後の育児では、体力面での配慮が重要になります。産後の回復には若い時よりも時間がかかる場合があり、新生児の世話と合わせて体力的な負担が大きくなることがあります。
産後の体力回復を促進するためには、適度な運動と十分な休息が必要です。ただし、無理をせず、体調に合わせて徐々に活動量を増やしていくことが大切です。また、家族や周囲のサポートを積極的に活用することも重要です。
育児では、特に夜間の授乳や夜泣きの対応で睡眠不足になりがちです。パートナーとの役割分担や、一時保育サービスの活用なども検討しましょう。自分の健康状態を把握し、無理をしないことが長期的な育児には大切です。
産後うつとマタニティブルーの違いとは?症状チェックと受診の目安について
家族・地域・制度を活用した育児サポート
高齢出産後の育児では、様々なサポートを活用することが重要です。家族のサポートはもちろん、地域の子育て支援センターや一時保育サービス、育児ヘルパーなどの専門的なサポートも検討しましょう。
多くの自治体では、高年初産婦向けの特別な支援制度を設けている場合があります。産後ケア事業や育児支援サービスなど、利用できる制度について事前に調べておくと良いでしょう。
また、同じような境遇の母親との交流も大切です。育児サークルや地域のコミュニティに参加することで、情報交換や精神的なサポートを得ることができます。
心と体を守るための長期的なケア
高齢出産後は、長期的な健康管理も重要な課題です。更年期の訪れが早い場合があり、ホルモンバランスの変化に注意する必要があります。定期的な健康診断を受け、必要に応じて専門医に相談することが大切です。
生活習慣病の予防も重要です。高血圧、糖尿病、骨粗鬆症などのリスクが高まる可能性があるため、適切な食事と運動習慣を維持することが必要です。
また、メンタルヘルスケアも忘れてはいけません。育児ストレスや体力の低下により、うつ状態になることもあります。早期に専門家に相談し、適切なケアを受けることが大切です。
医療技術の進歩で高齢出産はどう変わる?
出生前診断や胎児医療の進歩で、高齢出産の安全性は向上しています。個別化医療により、一人ひとりに合った管理が可能です。今後も再生医療などの発展により、選択肢が広がるでしょう。
出生前診断・胎児医療の進歩と高齢出産
近年の医療技術の進歩により、高齢出産の安全性は大幅に向上しています。出生前診断の精度向上、胎児治療の発達、新生児医療の進歩などにより、以前は困難とされていた症例でも良好な結果が得られるようになっています。
特に、NIPTをはじめとする出生前診断技術の発達により、早期に胎児の状態を把握し、適切な対応を取ることが可能になりました。また、胎児心拍数モニタリングや超音波検査の技術向上により、分娩時の安全性も向上しています。
新生児集中治療室(NICU)の設備充実や、周産期医療体制の整備により、高リスク出産に対する医療体制も強化されています。これらの技術進歩が、高齢出産の選択肢を広げています。
一人ひとりに合わせた“個別化医療”の重要性
高齢出産では、個々の患者の状況に応じた個別化医療が重要になります。年齢、既往歴、家族歴、生活習慣などを総合的に評価し、最適な管理方針を決定する必要があります。
遺伝子検査技術の発達により、個人の遺伝的背景を考慮した医療が可能になっています。薬物代謝に関する遺伝子多型や、疾患感受性遺伝子の解析により、より精密な医療が提供できるようになっています。
また、人工知能(AI)を活用した診断支援システムも開発されており、大量のデータから個別の予後予測や治療選択の支援が可能になっています。これらの技術により、高齢出産のリスク評価と管理がより精密になっています。
未来の高齢出産を支える医療技術の進化
高齢出産に関する医療技術は今後も発展が期待されています。再生医療技術の発達により、卵子の老化を防ぐ治療法や、卵巣機能を改善する治療法の開発が進んでいます。
また、遺伝子治療技術の発達により、遺伝性疾患の治療も可能になりつつあります。胚の遺伝子編集技術については倫理的な課題もありますが、将来的には遺伝性疾患の予防に活用される可能性があります。
遠隔医療の発達により、遠隔地でも専門的な医療を受けることが可能になっています。これにより、高齢出産の管理においても、より多くの患者が適切な医療を受けられるようになることが期待されています。
出産前に知っておきたい!産婦人科病院・助産院など産院の違いと里帰り出産の選び方のポイント
高齢出産に関するよくある質問
高齢出産について、多くのパパ・ママが疑問や不安を抱えています。ここでは、特によく寄せられる質問について、医学的根拠に基づいてお答えします。正しい情報を得ることで、不安の解消と適切な準備につながるでしょう。
Q.流産率は何歳から上がりますか?
A.流産率は30代半ば頃から徐々に増加し始め、特に35歳以降に顕著になります。具体的な数値を見ると、20代後半から30代前半では約10-15%程度ですが、35-39歳では約20-25%、40-44歳では約33-40%程度まで上昇します。ただし、これらは統計的な平均値であり、個人の健康状態や生活習慣によって大きく左右されます。
また、流産の多くは妊娠12週以前の早期流産で、その約80%が胎児の染色体異常によるものです。年齢が上がるほど卵子の老化が進み、染色体異常が起こりやすくなるため、流産率も上昇する傾向があります。
Q.高齢出産では特別な検査が必要ですか?
A.はい、高齢妊娠では通常の妊婦健診に加えて、特別な検査が推奨されます。主な検査として、染色体異常スクリーニング検査であるNIPT(非侵襲的出生前遺伝学的検査)や、確定診断のための羊水検査があります。
また、妊娠合併症の早期発見のため、血圧測定や血糖値検査、蛋白尿検査の頻度も増加します。胎児の発育状況をより詳しく確認するため、超音波検査も通常より頻繁に行われることがあります。通院間隔も短縮され、月に1回の検診が2週間に1回になる場合もあります。これらの検査により、母体と胎児の状態を密に監視し、問題があれば早期に対応することが可能になります。
Q.男性の年齢も妊娠に影響しますか?
A.はい、男性の年齢も妊娠と胎児に影響を与えることがわかっています。男性の妊孕性は女性ほど急激には低下しませんが、年齢とともに精子の質は徐々に低下し、40歳以降では明らかな変化が見られます。高齢の父親では、精子のDNA損傷率が上昇し、流産率の増加や一部の遺伝性疾患(自閉症、統合失調症など)のリスクが微増することが報告されています。
また、精子の運動性や濃度も年齢とともに低下し、自然妊娠率に影響を与える可能性があります。ただし、母体年齢ほど急激には変化せず、個人差も大きいのが特徴です。高年初婚カップルの場合、男性側も健康管理を意識し、禁煙・適度な運動・バランスの取れた食事を心がけることが推奨されます。
正しい知識と準備で安心して高齢出産に臨むために
高齢出産は35歳以上での初産と定義され、近年の晩婚化に伴い増加傾向にあります。確かに年齢とともに流産率や染色体異常のリスクは上昇しますが、適切な管理により多くの方が安全に出産されています。
重要なのは、正しい知識を持ち、妊娠前からの健康管理と専門医との連携を図ることです。医療技術の進歩により、高齢出産の安全性は大幅に向上しており、個別化医療により最適な管理が可能になっています。
不安や疑問がある場合は、一人で抱え込まず、産婦人科医に相談することをお勧めします。適切な情報と準備により、安心して妊娠・出産に臨むことができるでしょう。




