公開日 2025/08/12
【医師解説】切迫流産の症状・原因・治療法|流産・切迫早産との違いについて

目次
この記事の監修者
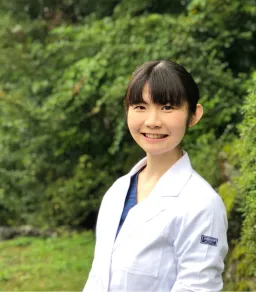
久保田産婦人科病院
西野 枝里菜 先生
妊娠中の女性やそのご家族にとって、「切迫流産」や「切迫早産」、「流産」という言葉を耳にすると大きな不安を感じる方も多いのではないでしょうか。これらは似ているようで異なる意味を持ち、特に切迫流産は適切な対応によって妊娠を継続できる可能性がある重要な状態です。
妊娠22週を境に流産と早産が区別されることや、切迫流産と切迫早産の違いを理解することは、安心して妊娠生活を送るうえで大切です。また、出血や腹痛など、どのような症状で医療機関を受診すべきかを知っておくことで、早期発見・早期対応につながります。
本記事では、産婦人科医として多くの妊婦さんと接してきた経験を基に、流産、切迫流産、切迫早産について詳しく解説します。それぞれの定義や原因、症状、対処法について正確な情報をお伝えし、パパ・ママが不安なく妊娠生活を送れるようサポートします。
妊娠初期症状はいつから出る?チェックポイントや診断方法について
流産ってどんな状態?
妊娠中に最も気になる流産について、その医学的な定義と分類を正しく理解しましょう。
流産は妊娠22週未満に起こる妊娠の中断を指し、発生時期や症状の有無によって分類されます。正確な知識を持つことで、必要以上に不安を感じることなく、適切な行動につなげられます。

流産の医学的な定義とは
流産とは、妊娠22週未満に妊娠が終了することを指します。日本産科婦人科学会の定義では、妊娠22週0日より前に胎児が母体外に出ることを流産と呼んでいます。この22週という基準は、胎児が母体外で生存できる可能性が極めて低いことから設定されています。
妊娠22週以降に妊娠が終了した場合は早産または死産と呼ばれ、流産とは区別されます。妊娠22週以降37週未満での出産が早産、妊娠22週以降で胎児が生存していない場合が死産となります。
流産の頻度は全妊娠の約10~15%で、決して珍しいことではありません。特に妊娠初期の流産は多く、妊娠を希望する女性の多くが経験する可能性があります。
初期流産と後期流産の違い
流産は発生時期により初期流産と後期流産に分けられます。初期流産は妊娠12週未満に起こる流産で、全流産の約80~90%を占めます。後期流産は妊娠12週以降22週未満に起こる流産です。
初期流産の特徴として、胎児の染色体異常が原因となることが多く、母体側の要因は少ないとされています。一方、後期流産では子宮頸管無力症や子宮奇形、感染症など母体側の要因が関与することが多くなります。
流産は症状の有無によっても分類されます。進行流産は出血や腹痛を伴い流産が進行している状態、完全流産は胎児や胎盤が完全に排出された状態、不全流産は一部が子宮内に残っている状態を指します。
妊娠超初期~妊娠初期におこる下痢・頭痛・腹痛・腰痛の症状と対処法
妊娠超初期~妊娠初期のおりものの症状とは?生理前と何が違う?知っておきたい量や色の特徴と対策
流産の主な原因
流産の原因は時期によって異なりますが、初期流産の約80%は胎児の染色体異常が原因とされています。これは偶発的に起こることが多く、両親の染色体に異常がなくても発生する可能性があります。
後期流産では、子宮頸管無力症、子宮奇形、子宮筋腫、感染症、血栓性疾患などが原因となることが多くなります。また、高齢出産では染色体異常のリスクが高まるため、年齢も流産のリスク要因の一つとなります。
ストレスや過度の運動、喫煙、過度の飲酒なども流産のリスクを高める要因とされています。しかし、日常生活での軽い運動や仕事のストレス程度で流産が起こることは少なく、過度に心配する必要はありません。
切迫流産とは?
切迫流産は適切な治療と安静により妊娠を継続できる可能性があります。出血や腹痛などの症状が現れたときの正しい受診タイミングと、治療内容を知っておきましょう。
不安を和らげるためにも、日常生活で気をつけたいポイントを確認しておくことが大切です。
切迫流産の定義
切迫流産とは、妊娠22週未満で流産の危険性が高い状態を指します。実際に流産が起こったわけではなく、胎児の心拍が確認でき、子宮口が閉じている状態です。適切な治療により妊娠を継続できる可能性があります。
切迫流産の症状には、性器出血、下腹部痛、腰痛などがあります。出血量は生理程度から大量まで様々で、色も鮮血から茶色っぽいものまで幅があります。痛みの程度も軽い違和感から強い痛みまで個人差があります。
切迫流産は妊娠初期から中期にかけて起こる可能性があり、妊娠8~12週頃に最も多く見られます。この時期は胎盤が完成する前で、ホルモンバランスが不安定になりやすいことが関係しています。
切迫流産でよくみられる症状
切迫流産の症状で最も注意すべきは性器出血です。妊娠中の出血は量に関わらず異常なサインであり、生理程度の出血でも医療機関への相談が必要です。出血の色が鮮血の場合は特に注意が必要で、緊急受診を検討してください。
下腹部痛や腰痛も重要な症状です。生理痛のような鈍痛から、陣痛のような規則的な痛みまで様々な形で現れます。痛みが持続する場合や強くなる場合は、速やかに医療機関を受診することが大切です。
つわりの軽快は必ずしも流産の兆候ではありません。妊娠12週前後になると、つわりが自然に軽快することが多く、これは正常な妊娠経過の一つです。しかし、つわりの急激な消失に加えて、下腹部痛や出血、体調の急激な変化がある場合は注意が必要です。体調の急激な変化を感じた場合は、自己判断せず医師に相談しましょう。
妊娠中の食べたほうが良いもの・食べられないものは?気持ち悪いつわり中でも食べられる食べ物は?
切迫流産と診断されたときの治療について
切迫流産の治療は安静が基本となります。医師の指示に従い、入院安静または自宅安静を行います。重度の場合は絶対安静が必要となり、トイレや食事以外はベッドで過ごすことになります。
薬物療法では、子宮収縮を抑制する薬や止血剤が使用されることがあります。また、プロゲステロンなどのホルモン剤で妊娠を維持する治療も行われます。これらの薬物治療は医師の厳密な管理のもとで行われます。
日常生活では、十分な休息と栄養摂取が重要です。ストレスを避け、規則正しい生活を心がけましょう。また、定期的な妊婦健診を受け、医師の指示に従って生活することで、妊娠継続の可能性を高めることができます。
切迫早産について|予防と管理
妊娠22週以降に起こる切迫早産は、適切な管理と治療で予後が大きく変わります。子宮収縮や子宮頸管長の変化など、見逃せない症状を理解しましょう。
早期発見と医療機関での適切な対応で、胎児の安全と母体の健康を守ることができます。
妊娠8ヶ月(28〜31週)|早産に注意!体調管理と出産準備リスト
切迫早産の定義
切迫早産とは、妊娠22週以降37週未満で早産になる危険性が高い状態を指します。子宮収縮が頻繁に起こり、子宮頸管が短縮または開大している状態ですが、まだ分娩に至っていない段階です。
切迫早産は妊娠28~34週頃に最も多く発生します。この時期は胎児の発育が活発で、子宮が大きくなることで子宮頸管に負担がかかりやすくなります。また、胎児の体重増加により羊水量も増加し、子宮内圧が高まることも関係しています。
妊娠22週以降の早産は胎児の生存可能性があるため、妊娠継続のための積極的な治療が行われます。週数が進むほど胎児の予後は良好になるため、少しでも妊娠期間を延長することが重要です。
妊娠8ヶ月(28〜31週)|早産に注意!体調管理と出産準備リスト
切迫早産で気をつけたい症状
切迫早産の主な症状は規則的な子宮収縮です。1時間に6回以上の子宮収縮が起こり、お腹の張りや痛みを感じます。初めは軽い張り程度でも、徐々に強くなり規則的になることが特徴です。
子宮頸管長の短縮も重要な指標です。通常、妊娠中期から後期にかけて子宮頸管長は35mm以上ありますが、25mm以下になると切迫早産のリスクが高くなります。経腟超音波検査により子宮頸管長の測定が行われます。
危険因子として、多胎妊娠、前回の早産既往、子宮奇形、子宮筋腫、妊娠中の感染症、高齢出産などがあります。また、重労働や長時間立ち仕事、強いストレスなども切迫早産のリスクを高める要因となります。
切迫早産の治療方法について
切迫早産の治療は安静が基本になります。リトドリンやマグネシウムなどの点滴により子宮収縮を抑制し、妊娠期間の延長を図ることや重症例では長期間の入院安静が必要となることもあります。
子宮頸管縫縮術(シロッカー手術)は、子宮頸管無力症が原因の場合に行われる外科的治療です。子宮頸管を糸で縫い縮めることで早産を予防します。手術は妊娠中期に行われることが多く、分娩時には抜糸が必要です。
予防策として、定期的な妊婦健診での早期発見が重要です。子宮頸管長の測定や感染症の検査により、切迫早産の兆候を早期に発見できます。また、適度な休息と栄養摂取、ストレス管理により予防効果が期待できます。
流産・切迫流産・切迫早産の違いについて
似ているようで異なるこれら3つの状態を正確に区別することは、適切な対応のために重要です。妊娠22週を境にした分類の意味や、それぞれの症状の特徴を整理しておきましょう。
受診すべき症状を理解し、緊急性の判断ができるように備えてください。
妊娠22週を境に変わる医学的な意味
妊娠22週0日という基準は、胎児が母体外で生存できる可能性の境界線として設定されています。この週数以前は流産、以降は早産と分類されるため、医学的な対応も大きく異なります。
妊娠22週未満では胎児の肺や各臓器の発達が不十分で、母体外での生存は困難です。そのため、この時期の妊娠終了は流産として扱われ、胎児の救命よりも母体の安全を優先した治療が行われます。
一方、妊娠22週以降では胎児の生存可能性があるため、早産として積極的な治療が行われます。新生児集中治療室(NICU)での管理により、早産児の救命率は向上しています。
流産・切迫流産・切迫早産の重要な見分について
流産では持続的な出血と強い下腹部痛が特徴的です。出血量は徐々に増加し、血塊を伴うことが多くなります。痛みは陣痛様で、間隔が短くなる傾向があります。
切迫流産では軽度から中等度の出血と軽い腹痛が見られます。胎児の心拍が確認でき、子宮口が閉じているため、適切な治療により妊娠継続が可能です。症状の程度は個人差が大きく、軽微な出血のみの場合もあります。
切迫早産では規則的な子宮収縮が最も重要な症状です。1時間に6回以上の収縮があり、お腹の張りや痛みを感じます。破水や大量の帯下、腰痛なども伴うことがあります。
すぐに受診すべき症状とは?
妊娠中の出血は量に関わらず受診が必要です。特に鮮血の場合や血塊を伴う場合は緊急性が高く、速やかな受診が必要です。生理程度の出血でも自己判断せず、医療機関に相談することが大切です。
強い腹痛や規則的な子宮収縮も重要な症状です。痛みが持続する場合や間隔が短くなる場合は、緊急受診を検討してください。特に妊娠22週以降では切迫早産の可能性があるため、早急な対応が必要です。
破水や意識消失などの症状が現れた場合も、迷わず緊急受診してください。これらの症状は重篤な合併症の可能性があり、母体と胎児の生命に関わることがあります。
予防法と日常生活での注意点
流産や切迫早産を予防するには、毎日の生活習慣が大きな役割を果たします。喫煙や感染症を避けること、高齢出産や多胎妊娠に備えたリスク管理が大切です。
母体と赤ちゃんの健康を守るためにできることを、今日から実践していきましょう。
流産を防ぐための生活習慣
流産の予防法として最も重要なのは、規則正しい生活習慣の維持です。十分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動により、母体の健康状態を良好に保つことができます。
喫煙と飲酒は流産のリスクを高める要因として知られています。妊娠を希望する場合は妊娠前から禁煙・禁酒を心がけ、パートナーにも協力を求めることが大切です。受動喫煙も胎児への影響があるため注意が必要です。
妊娠中の感染症対策
感染症は流産や早産の原因となるため、予防対策が重要です。手洗いとうがいを徹底し、人混みを避けることで感染リスクを減らせます。特に妊娠初期は免疫力が低下しやすいため注意が必要です。
トキソプラズマ、リステリア、サイトメガロウイルスなどの感染症は胎児に影響を与える可能性があります。生肉の摂取を控え、食材の十分な加熱を心がけましょう。
性感染症の検査と治療も重要です。クラミジア、梅毒などの性感染症は早産や流産の原因となるため、妊娠初期の検査で発見された場合は適切な治療を受けることが必要です。
高齢出産や多胎妊娠でのリスク管理
高齢出産では染色体異常のリスクが高まるため、より慎重な管理が必要です。35歳以上の妊娠では出生前診断について医師と相談し、必要に応じて検査を受けることも選択肢の一つです。
多胎妊娠では早産のリスクが高いため、定期的な子宮頸管長の測定が重要です。また、母体への負担も大きくなるため、十分な休息と栄養摂取が必要です。
子宮筋腫がある場合は、妊娠中の筋腫の変化に注意が必要です。筋腫の大きさや位置により流産や早産のリスクが高まることがあるため、定期的な超音波検査による経過観察が重要です。
高齢出産は何歳から?高齢出産のリスクと対策を医師が詳しく解説
妊娠や赤ちゃんへの影響について
流産や切迫早産を経験した後の胎児への影響と、次回妊娠への備えを知っておきましょう。適切な時期を見極め、十分な準備をすることで次の妊娠の成功率を高めることができます。医師との相談を大切にして、安心して妊娠計画を進めてください。
流産が胎児に与える影響
流産は胎児の発育停止を意味するため、胎児への直接的な影響はありません。しかし、流産の原因となった要因が今後の妊娠に影響を与える可能性があります。
染色体異常による流産は偶発的なものが多く、次回妊娠への影響は限定的です。しかし、両親のいずれかに染色体異常がある場合は、遺伝カウンセリングを受けることが推奨されます。
習慣流産(3回以上の連続した流産)の場合は、詳しい原因検索が必要です。自己免疫疾患、血栓性疾患、子宮奇形などが原因となることがあり、適切な治療により次回妊娠の成功率を高めることができます。
切迫早産による早産児への影響
切迫早産により早産となった場合、胎児の在胎週数により予後が大きく異なります。妊娠28週以降の早産では比較的良好な予後が期待できますが、それ以前では合併症のリスクが高くなります。
早産児の主な合併症には、呼吸窮迫症候群、脳室内出血、壊死性腸炎、未熟児網膜症などがあります。これらの合併症は在胎週数が短いほど発生率が高くなります。
新生児集中治療室での管理により、早産児の救命率と予後は大幅に改善されています。また、妊娠中のステロイド投与により胎児の肺成熟を促進し、呼吸器合併症のリスクを減少させることができます。
次の妊娠に向けてできる準備
流産や早産の既往がある場合、次回妊娠では特に注意深い管理が必要です。妊娠前から葉酸サプリメントの摂取、生活習慣の改善、基礎疾患の治療などを行うことが重要です。
定期的な妊婦健診では、前回の妊娠歴を医師に詳しく伝えることが大切です。リスク要因に応じた個別的な管理計画を立てることで、次回妊娠の成功率を高めることができます。
流産や切迫流産・切迫早産に関するよくある質問と回答
妊娠中の流産や切迫流産、切迫早産について、多くの妊婦さんとご家族から寄せられる質問にお答えします。正しい知識を持つことで、不安を軽減し適切な対応ができるようになります。
Q.出血が少量でも病院に行くべきでしょうか?
A.妊娠中の出血は量に関わらず、必ず医療機関に相談することをお勧めします。少量の出血でも切迫流産や切迫早産の初期症状である可能性があるためです。
特に鮮血の場合は緊急性が高く、速やかな受診が必要です。生理程度の出血であっても自己判断せず、まずは産婦人科クリニックに電話で相談し、医師の指示に従ってください。出血の色、量、持続時間、随伴症状などを詳しく伝えることで、適切な判断を受けることができます。夜間や休日であっても、症状が強い場合は救急外来への受診を検討してください。
Q.つわりが急になくなったのですが、流産の兆候でしょうか?
A.つわりの軽快は必ずしも流産の兆候ではありません。妊娠12週前後になると、つわりが自然に軽快することが多く、これは正常な妊娠経過の一つです。しかし、つわりの急激な消失に加えて、下腹部痛や出血、体調の急激な変化がある場合は注意が必要です。
また、妊娠検査薬の反応が薄くなる場合は、hCGホルモンの低下を示している可能性があり、胎児の発育停止が疑われます。つわりの変化だけでなく、他の症状も併せて観察し、心配な場合は医療機関で超音波検査や血液検査を受けることが大切です。
Q.切迫早産と診断されました。どのような治療を受けることになりますか?
A.切迫早産の治療は、主に安静療法と薬物療法が中心となります。症状の程度により自宅安静から入院安静まで様々で、重症例では絶対安静が必要となることもあります。薬物療法では、子宮収縮を抑制するリトドリンやマグネシウムの点滴投与が行われます。子宮頸管無力症場合は、子宮頸管縫縮術という外科的治療を検討することもあります。
治療期間は個人差がありますが、妊娠37週まで継続することが目標となります。治療中は定期的な超音波検査や胎児心拍モニタリングにより、母体と胎児の状態を注意深く観察します。医師の指示に従い、適切な治療を受けることで妊娠継続の可能性を高めることができます。
産後うつとマタニティブルーの違いとは?症状チェックと受診の目安について
適切な対応と定期健診でリスクを最小限に抑えよう
流産、切迫流産、切迫早産について正しい知識を持つことは、妊娠中の不安を軽減し、適切な対応を取るために重要です。妊娠22週を境に流産と早産が区別され、それぞれ異なる対応が必要となります。
これらの症状が現れた場合は、自己判断せずに医療機関に相談することが最も大切です。早期発見・早期治療により、妊娠継続の可能性を高めることができます。日頃から規則正しい生活習慣を心がけ、定期的な妊婦健診を受けることで、リスクを最小限に抑えることができます。
妊娠は一人ひとり異なる経過をたどるため、不安や疑問があれば遠慮なく医師に相談してください。正しい知識と適切な医療サポートにより、安心して妊娠生活を送ることができるでしょう。




