公開日 2025/08/12
【医師解説】産後うつとマタニティブルーの違いとは?症状チェックと受診の目安について

目次
この記事の監修者
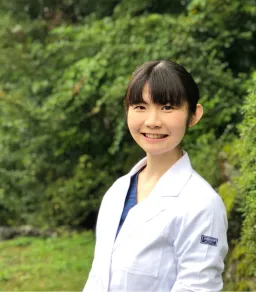
久保田産婦人科病院
西野 枝里菜 先生
妊娠中から産後にかけて、多くの女性が気分の落ち込みやイライラ、不安感などの心の変化を経験します。よく耳にする「マタニティブルー」や「産後うつ」は、似ているように思えても発症時期や症状の程度、必要な対応に違いがあります。
この記事では、産婦人科医の視点からそれぞれの症状と対処法を解説し、心の健康を保つための生活習慣や家族のサポート方法も紹介します。産後の心の変化に不安を感じている方、身近な人を支えたい方はぜひ参考にしてください。
マタニティブルーと産後うつの違いとは?

妊娠・出産に伴う心の変化の中でも、多くの方が気になるのが「マタニティブルー」と「産後うつ」です。似ているようで発症時期や症状の程度、経過の目安などが異なります。
マタニティブルーと産後うつはいつから発症する?
マタニティブルーは産後3〜5日頃から始まり、通常は2週間以内に自然に改善します。
一方、産後うつは産後2週間以降〜数か月の間に発症し、日常生活に支障をきたすほどの気分の落ち込みや不安が続くため、治療が必要な病気とされています。
マタニティブルー | 産後うつ | |
|---|---|---|
主な症状 | 涙脆さ、不安定さ、イライラなど | 強い気分の落ち込み、不安、無気力、罪悪感など |
経過の目安 | 産後3〜5日頃から始まり、産後2週間以内に自然に改善することが多い | 産後2週間から数か月の間に発症し、2週間以上続き日常生活に支障をきたす可能性がある |
医学的治療 | 基本的に不要(休養・サポートなどで改善) | 必要になることが多い(カウンセリングや薬物療法など) |
医療機関への相談の目安
マタニティブルーと産後うつの症状は似ていますが、続く期間や生活への影響が大きな違いです。症状が2週間以上続く場合や、育児や日常生活に支障を感じる場合は、早めに医療機関へ相談しましょう。
陣痛の間隔はどれくらい?どんな痛み?前駆陣痛と本陣痛の違いまで詳しく解説
マタニティブルーとは?症状の特徴と原因・乗り越え方
マタニティブルーは、産後間もない時期に多くの女性が経験する自然な心の変化です。ホルモンバランスの急激な変化が主な原因とされており、一時的な症状として捉えられています。症状の特徴と対処法を詳しく見ていきましょう。
マタニティブルーの主な症状とチェックポイント
マタニティブルーは、産後間もない時期に多くの女性が経験する一時的な心の変化です。病気ではなく自然な現象とされていますが、症状が続くと不安になることもあります。
主な症状は以下の通りです。
- 理由もなく涙が出る
- 気分が不安定になる
- イライラしやすい
- 不安感が強くなる
- 疲労感や集中力の低下
これらの症状は、出産直後のホルモンバランスの変化によるものであり、病気ではありません。多くの場合、産後1〜2週間で自然に改善していきます。ただし、症状が長引く場合は産後うつの可能性も考慮する必要があります。
マタニティブルーが起こる原因は?ホルモン変化との関係
マタニティブルーの主な原因は、出産後のホルモンバランスの急激な変化です。妊娠中に高まっていたエストロゲンやプロゲステロンが出産直後に急激に低下し、脳内の神経伝達物質のバランスが崩れます。
さらに、以下の要因も複合的に影響します。
- 出産による身体的疲労
- 育児に対する不安やストレス
- 生活環境や人間関係の変化
これらの要因が複合的に作用することで、マタニティブルーが発症すると考えられています。
マタニティブルーの乗り越え方とセルフケアの工夫
マタニティブルーへの乗り越え方として、まずは十分な休息を取ることが重要です。産後の身体は回復期にあるため、無理をせず、家族や周囲の人にサポートを求めましょう。
また、規則正しい生活リズムを心がけ、栄養バランスの良い食事を摂ることも大切です。軽い運動やストレッチ、リラクゼーション法なども症状の改善に役立ちます。一人で抱え込まず、パートナーや家族と感情を共有することも重要な対処法の一つです。
産後うつとは?症状の特徴と原因・治療方法

産後うつは、マタニティブルーとは異なり、医学的な治療が必要な病気です。症状が長く続き、日常生活や育児に大きな支障をきたすため、早期の発見と適切な治療が重要です。
産後うつの主な症状とチェックポイント
産後うつの主な症状には以下のようなものがあります。
- 強い気分の落ち込み、絶望感、無力感、罪悪感
- 赤ちゃんへの愛情を感じにくい
- 育児への不安や恐怖感
- 睡眠障害や食欲不振、疲労感
- 集中力の低下や決断力の欠如
- 自分を責める気持ちが強い
重症の場合は、自分や赤ちゃんを傷つけたいという気持ちが生じることもあり、この場合は早急な治療が必要です。
産後うつが起こる原因とリスク要因
産後うつの発症には、生物学的要因、心理学的要因、社会的要因が複合的に関与しています。ホルモンバランスの変化に加えて、育児ストレス、睡眠不足、社会的サポートの不足、経済的な問題なども発症リスクを高めます。
また、うつ病の既往歴がある場合、妊娠中にうつ症状があった場合、家族歴がある場合なども、産後うつの発症リスクが高くなります。これらのリスク要因を理解し、予防や早期発見に役立てることが大切です。
産後うつの治療と乗り越え方
産後うつの治療には、カウンセリング、薬物治療、社会的サポートなどが含まれます。社会的サポートとは、家族や地域のサポートを受け、出産への負担を一人で抱え込まないようにすることです。軽度から中等度の場合は、認知行動療法などのカウンセリングが効果的です。
重度の場合は、抗うつ薬による薬物治療が検討されます。授乳中の薬物治療については、医師と相談して安全性を確認しながら進めることが重要です。また、家族や友人からのサポート、産後ケアセンターの利用、育児サポートサービスの活用なども治療の一環として重要です。
出産前に知っておきたい!産婦人科病院・助産院など産院の違いと里帰り出産の選び方のポイント
産後の心の健康を守る生活のポイント
産後はホルモンバランスや生活リズムの変化で心が不安定になりやすい時期です。日常の習慣を工夫したり、周囲のサポートを活用することで、マタニティブルーや産後うつの予防や軽減につながります。
産後うつ予防のための生活習慣
・睡眠と休息を十分にとる
良質な睡眠は心の健康にとって不可欠です。妊娠中は体の変化により睡眠の質が低下しやすく、産後は授乳や夜泣きで睡眠不足になりがちです。できるだけ規則正しい睡眠リズムを維持し、昼寝も活用しましょう。
睡眠環境を整えることも重要です。寝室の温度や湿度を適切に保ち、リラックスできる環境を作りましょう。また、就寝前のスマートフォンやテレビの使用は控え、リラックスできる活動に時間を使うことをお勧めします。
・栄養バランスと食事に気をつける
栄養バランスの良い食事は、心の健康にも大きく影響します。特に、オメガ3脂肪酸、ビタミンB群、ビタミンD、鉄分などは脳の健康と関連が深いとされています。
規則正しい食事時間を心がけ、バランスの良い食事を摂るようにしましょう。また、妊娠中や授乳中は特に栄養需要が高まるため、医師や栄養士と相談して適切な栄養摂取を心がけることが大切です。
・運動やリラクゼーションでリフレッシュを
妊娠中や産後に適した軽い運動は、心の健康維持に効果的です。ウォーキング、マタニティヨガ、ストレッチなどが推奨されています。運動は血行を促進し、エンドルフィンの分泌を促すことで、気分の改善に役立ちます。
また、リラクゼーション法として、深呼吸、瞑想、アロマテラピーなども有効です。これらの方法は、ストレスを軽減し、心の平静を保つのに役立ちます。運動やリラクゼーション法を日常に取り入れることで、心の健康を維持しやすくなります。
産後うつを防ぐための周囲のサポート
妊娠中から産後にかけて、家族や周囲の人々からのサポートは非常に重要です。家族や周りの人に頼れる関係を作っておくと、心の健康を守りやすくなり、つらさを抱え込みにくくなります。
・パートナーからのサポート
パートナーからの理解とサポートは、妊娠中や産後の心の健康にとって欠かせません。パートナーは、妊娠中のうつや産後うつの症状について理解し、適切なサポートを提供することが重要です。
具体的には、家事や育児の分担、メンタル面でのサポート、医療機関への受診の手伝いなどが挙げられます。また、パートナー自身もストレスを感じることがあるため、お互いにコミュニケーションを取り、支え合うことが大切です。
・家族や友人からのサポート
家族や友人からのサポートも、心の健康維持に重要な役割を果たします。特に、育児経験のある女性からのアドバイスや、実際に出産までのサポートを受けることは貴重です。
ただし、サポートを受ける際は、自分にとって本当に必要な支援かどうか見極めることが重要です。時には、過度なアドバイスや干渉がストレスになることもあるため、適切な距離感を保ちながらサポートを受けることを心がけましょう。
・専門機関からのサポート
産後ケアセンター、子育て支援センター、保健センターなどの専門機関も積極的に活用しましょう。これらの機関では、専門的なアドバイスやサポートを受けることができます。
また、同じような経験をしている他の母親との交流も心の支えになります。母親学級や育児サークルなどに参加することで、情報交換や相互支援が可能になります。必要に応じて、カウンセリングサービスや精神科医への紹介も受けることができます。
出産準備・マタニティマーク・母子手帳の「いつから・どこで・どうやって」を分かりやすく解説
産後うつ・マタニティブルーに関するよくある質問
妊娠や出産を経験すると、気分の落ち込みや不安、イライラなど心の変化に戸惑う方は少なくありません。ここでは、マタニティブルーや産後うつに関して寄せられる代表的な質問と、その回答をまとめました。
Q.身近な人に打ち明けるのが恥ずかしい、大げさだと思われそうで心配です、どうしたらよいでしょうか?
A.心理的な問題を打ち明けることは決して恥ずかしいことではありません。妊娠中や産後の心の変化は、多くの女性が経験する自然な現象です。まずは、信頼できる家族や友人に少しずつ気持ちを話してみることから始めましょう。最初は「最近気分が落ち込みがちなの」といった軽い表現から始めても構いません。
また、医療機関では守秘義務があるため、安心して相談できます。産婦人科医や助産師、保健師などの専門家は、このような症状について豊富な知識と経験を持っているため、適切なアドバイスを受けることができます。一人で抱え込まず、勇気を出して周囲に助けを求めることが回復への第一歩となります。
Q.授乳中の薬物治療は本当に安全ですか?
A.授乳中の薬物治療については、医師の指導のもとで適切に行えば安全性が高いとされています。現在では、授乳中でも比較的安全に使用できる抗うつ薬があり、医師は母乳への移行量、赤ちゃんへの影響、母体の症状の重さなどを総合的に判断して薬剤を選択します。
また、薬物治療を行う場合は、赤ちゃんの様子を定期的に観察し、必要に応じて血液検査を行うこともあります。治療の効果と安全性を最大限に確保するために、医師との密接な連携が不可欠です。薬物治療に不安がある場合は、遠慮なく医師に相談し、十分な説明を受けることが重要です。場合によっては、薬物治療以外の選択肢も検討できるため、医師と相談して最適な治療方針を決定しましょう。
Q.上の子がいる場合、どのように対応したら良いですか?
A.上の子がいる場合、育児の負担が大きくなるため、家族全体で協力体制を築くことが重要です。まず、パートナーと役割分担を明確にし、上の子の世話や家事を分担しましょう。また、祖父母や親戚、友人などからのサポートも積極的に活用することをお勧めします。
上の子には、年齢に応じて状況を説明し、理解を求めることも大切です。「ママは今少し疲れているから、みんなで協力しようね」といった具体的な声かけが有効です。保育園や幼稚園の利用、一時保育サービス、ファミリーサポートセンターなどの社会資源も活用しましょう。また、上の子との特別な時間を作ることで、不安を軽減し、安心感を与えることができます。完璧を求めすぎず、できる範囲で対応することが重要です。
症状に気づいたら、適切な対処とサポートを
マタニティブルー、産後うつは、それぞれ異なる特徴を持つ心の変化です。マタニティブルーは産後の一時的な症状で自然に改善することが多いですが、産後うつは医学的な治療が必要な病気として捉える必要があります。これらの症状は、ホルモンバランスの変化、育児ストレス、社会的サポートの不足など、複数の要因が関与して発症します。早期発見と適切な対処により、症状の改善と心の健康維持が可能になります。
一人で抱え込まず、家族や友人、医療機関からのサポートを積極的に活用することが重要です。心の健康は、母親自身だけでなく、家族全体の幸福に直結します。症状に気づいたら、恥ずかしがらずに専門家に相談し、安心して子育てに向き合える環境を整えましょう。




