公開日 2025/08/12
【医師解説】初めての出産で気になる無痛分娩|メリット・デメリット・費用・和痛分娩との違い

目次
この記事の監修者
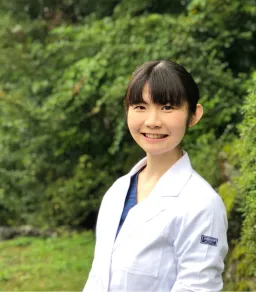
久保田産婦人科病院
西野 枝里菜 先生
出産に対する不安の中でも、陣痛の痛みは多くの妊婦さんが心配する大きな要因です。「どれくらい痛いのか」「痛みを軽減する方法はあるのか」と不安に思うのは自然なことです。無痛分娩や和痛分娩は、そのような痛みを軽減する方法のひとつとして選ばれています。
この記事では、産婦人科医として無痛分娩と和痛分娩の基本的な違い、期待できる痛み軽減効果、そして知っておくべきリスクについて解説します。パパ・ママが安心して出産方法を選べるよう、医学的根拠に基づいた情報をお伝えします。
無痛分娩とは?

無痛分娩は、主に硬膜外麻酔を使用して陣痛時から出産時まで強い疼痛緩和効果を目指す分娩方法です。麻酔薬を脊椎の周りにある硬膜外腔に注入することで、痛みの神経伝達を遮断し、陣痛の痛みをほぼ完全に取り除くことを目的としています。ただし、「無痛」という名称であっても、実際には完全にゼロにならないケースもあることを理解しておく必要があります。
硬膜外麻酔による無痛分娩では、下半身の感覚が鈍くなるため、陣痛の痛みを感じにくくなります。この方法は欧米では一般的に行われており、日本でも実施する医療機関が増えています。麻酔の効果により、お母さんは陣痛中もリラックスして過ごすことができ、出産時のストレスを大幅に軽減できます。
無痛分娩で痛みはどれくらい軽減される?
硬膜外麻酔による無痛分娩では、陣痛の痛みを80〜90%程度軽減できるとされています。多くの場合、陣痛の強い痛みはほとんど感じなくなり、お腹の張りや圧迫感程度の感覚は残ることが一般的です。完全に痛みがゼロになるわけではありませんが、通常の陣痛と比較すると劇的な痛みの軽減が期待できます。
無痛分娩の効果は個人差があり、体質や麻酔の効き方によって変わります。一部の方では、麻酔が十分に効かない場合や、分娩の進行に伴って痛みを感じる場合もあります。また、会陰切開や縫合時の痛みについては、別途局所麻酔が必要になることもあります。
陣痛の間隔はどれくらい?どんな痛み?前駆陣痛と本陣痛の違いまで詳しく解説
無痛分娩にリスクはある?
無痛分娩で最も一般的な副作用は、麻酔による血圧低下です。硬膜外麻酔により交感神経がブロックされることで、血管が拡張し血圧が下がることがあります。この血圧低下は、一時的に胎盤への血流を減少させ、胎児の心拍数に変化をもたらす可能性があります。そのため、無痛分娩中は母体と胎児の状態を継続的にモニタリングすることが必要です。
その他の副作用として、頭重感、吐き気、一過性の下肢の運動障害などが報告されています。稀ではありますが、重篤な副作用として呼吸抑制が起こる場合もあります。また、麻酔針の刺入時に硬膜を誤って穿刺してしまう硬膜穿刺や、感染症のリスクも考慮する必要があります。
胎児への影響について
無痛分娩による麻酔薬の胎児への直接的な影響は少ないとされていますが、間接的な影響は考慮する必要があります。最も重要なのは、母体の血圧低下による胎盤循環の一時的な減少です。これにより、胎児の心拍数が変化することがあり、場合によっては緊急帝王切開が必要になることもあります。
胎児への影響を最小限に抑えるため、無痛分娩中は胎児心拍数モニタリングを継続的に行い、異常があれば速やかに対処することが重要です。また、麻酔の投与量や投与時期を適切に調整することで、これらのリスクを軽減できます。
無痛分娩にかかる費用はどれくらい?
無痛分娩は、健康保険が適用されないため基本的に自己負担となります。
費用の相場
通常の分娩費用に加えて、10〜20万円程度の追加費用がかかるのが一般的です。金額や内訳は医療機関によって大きく異なります。
追加費用がかかるケース
- 前日からの入院や処置(ラミナリアなど頸管を広げる処置)が必要な場合
- 陣痛促進剤の使用など、分娩管理に追加の医療行為が行われた場合
- 麻酔科医の常勤・待機体制や施設の設備による違い
出産一時金について
分娩費用は出産育児一時金(原則50万円)が適用されますが、無痛分娩の追加費用は含まれないため、自己負担額が発生する点には注意が必要です。
同じ「無痛分娩」という名称でも、病院によって実施方法や管理体制が異なるため、事前に費用の目安と追加費用の有無を確認することが重要です。
病院選びで確認しておきたいポイント

痛分娩を安心して受けるには、病院の体制や対応を事前に確認しておくことが大切です。ここでは病院選びの際に注目しておきたいポイントを紹介します。
医療機関での安全管理体制
安全な無痛分娩を提供するためには、医療機関での適切な管理体制が必要です。まず、麻酔科医や産科医による十分な技術と経験が重要です。無痛分娩を行う医療機関では、24時間体制での麻酔管理が可能で、緊急時に迅速に対応できる体制を整えています。
また、母体と胎児の状態を継続的にモニタリングする設備と、異常が発生した場合の緊急対応システムが整備されています。血圧低下や胎児心拍数異常などの合併症が発生した場合には、速やかに治療を開始し、必要に応じて緊急帝王切開に移行できる体制が確保されています。
帝王切開の気になるを解説!術後の痛みや傷跡、入院期間はどうなる?
事前の検査とカウンセリング
無痛分娩を安全に行うためには、事前の十分な検査と評価が重要です。妊娠中の健康状態、既往歴、アレルギー歴、服用中の薬剤などを詳しく確認します。特に、出血傾向や脊椎の異常がある場合は、無痛分娩が適応できない場合があります。
また、麻酔に対する不安や疑問がある場合は、事前に麻酔科医との面談を行い、十分な説明を受けることが大切です。この際、麻酔の方法、期待される効果、起こりうる副作用やリスクについて詳しく説明を受け、納得したうえで同意することが重要です。
分娩中の適切な管理
分娩中は、母体と胎児の状態を継続的にモニタリングし、異常の早期発見と対処を行います。血圧、心拍数、酸素飽和度などの母体のバイタルサインと、胎児心拍数モニタリングを継続的に行います。麻酔の効果や副作用についても定期的に評価し、必要に応じて麻酔の追加投与や調整を行います。
また、分娩の進行状況に応じて、陣痛促進剤の使用や器械分娩の適応についても適切に判断します。無痛分娩では陣痛が弱くなることがあるため、分娩進行の遅延が認められる場合は、オキシトシンによる陣痛促進が行われることがあります。
出産前に知っておきたい!産婦人科病院・助産院など産院の違いと里帰り出産の選び方のポイント
無痛分娩を検討するときに考えておきたいこと
無痛分娩を選択する際は、様々な要因を総合的に考慮する必要があります。個人の状況や希望に応じた最適な選択をするための判断基準について説明します。
医学的な条件と禁忌事項
無痛分娩には、医学的な適応と禁忌事項があります。適応となる場合には、強い陣痛恐怖症、高血圧や心疾患などの合併症がある場合、前回の分娩で強い痛みを経験した場合などが挙げられます。一方、禁忌事項には、出血傾向、脊椎の異常、感染症、麻酔薬に対するアレルギーなどがあります。
これらの医学的な条件について、担当医と十分に相談し、個人の状況に応じた最適な方法を選択することが重要です。また、妊娠経過中に状況が変化する場合もあるため、定期的な評価と見直しが必要です。
個人の価値観
無痛分娩の選択は、医学的な要因だけでなく、個人の価値観や希望も重要な判断基準となります。自然な分娩を希望する方もいれば、痛みを軽減して快適な分娩を希望する方もいます。また、初産か経産かによっても考え方が変わる場合があります。
パートナーや家族の理解と支援も重要な要素です。分娩方法について家族と十分に話し合い、共通の理解を得ることで、より安心して分娩に臨むことができます。
医療機関の選択
無痛分娩を希望する場合は、これらの方法を安全に提供できる医療機関を選択することが重要です。医療機関の選択基準には、麻酔科医の常勤体制、緊急時の対応能力、実績と経験、設備の充実度などが含まれます。
また、医療機関によって無痛分娩の実施方針や費用が異なるため、事前に詳しく確認することが大切です。可能であれば、複数の医療機関を比較検討し、自分に最も適した施設を選択することをお勧めします。
無痛分娩を希望する方が準備しておきたいこと
妊娠が判明したら、できるだけ早い時期から分娩方法について情報収集を始めることが重要です。産科医や助産師から基本的な情報を収集し、無痛分娩について理解を深めます。また、実際にこれらの方法で分娩を経験した方の体験談を聞くことも参考になります。
妊娠中期頃から、具体的な分娩方法について医師と相談を始めることをお勧めします。この時期には、妊娠の経過も安定しており、分娩に向けた準備を計画的に進めることができます。
バースプランの作成
分娩に対する希望や不安を整理し、バースプランを作成することが有効です。バースプランには、希望する分娩方法、痛み軽減の程度、分娩時の環境、立ち会い出産の希望などを含めます。このプランを医療スタッフと共有することで、より個人に合った分娩ケアを受けることができます。
ただし、バースプランは柔軟に変更できるものとして考えることが重要です。分娩の進行状況や緊急事態により、計画通りに進まない場合もあることを理解しておきましょう。
出産準備はいつから?妊娠期別の準備ポイントと母子手帳・マタニティマークの取得方法について
知っておきたい分娩開始のタイミング
無痛分娩の開始タイミングは、医療機関によって方針が異なりますが、一般的に陣痛が始まり、子宮口が4〜5cm開大した段階で開始されることが多いです。早すぎる開始は分娩進行を遅らせる可能性があり、遅すぎる開始は十分な効果が得られない場合があります。
また、計画分娩として陣痛促進剤を使用して分娩を誘発する場合もあります。この場合は、事前に入院し、管理された環境で分娩を進めることができます。タイミングの判断は、母体と胎児の状態を総合的に評価して決定されます。
妊娠10ヶ月(36〜40週)|出産直前!陣痛・破水の兆候とお産への心構え
和痛分娩についても知っておこう
無痛分娩と並んで耳にすることが多いのが「和痛分娩」です。和痛分娩は、痛みを完全に除去するのではなく、軽減することを目的とした分娩方法です。麻酔薬の投与や、呼吸法、瞑想、姿勢の工夫などの非薬物アプローチを中心とした方法が用いられます。無痛分娩と比較して、より自然な分娩に近い状態を保ちながら、痛みを和らげることが特徴です。
和痛分娩の方法には、薬物を使用する場合と使用しない場合があります。薬物を使用する場合は、静脈内に鎮痛剤を投与したり、笑気ガスを吸入したりする方法があります。非薬物的な方法では、リラクゼーション技法、呼吸法、マッサージ、温熱療法、分娩時の体勢の工夫などが用いられます。また、病院によっては硬膜外麻酔を使用する場合でも、和痛分娩と呼ぶことがあります。
和痛分娩の痛み軽減効果
和痛分娩による痛み軽減効果は、使用する方法によって大きく異なります。静脈麻酔薬を使用する場合は、痛みを30〜50%程度軽減できることが多いですが、完全に痛みがなくなることはありません。非薬物的な方法では、痛み自体の軽減効果は限定的ですが、リラクゼーション効果により痛みの感じ方や不安感を和らげることができます。
呼吸法やリラクゼーション技法による和痛分娩では、痛みの強さよりも、痛みに対する対処能力を向上させることが主な目的となります。これらの方法は、痛みを完全に取り除くことはできませんが、出産時のストレスを軽減し、より前向きな気持ちで分娩に臨むことができます。
和痛分娩のリスク
和痛分娩のリスクは、使用する方法によって異なります。静脈麻酔薬を使用する場合は、薬剤による副作用として眠気、めまい、呼吸抑制などが起こる可能性があります。笑気ガスを使用する場合は、吐き気や頭痛が生じることがあります。非薬物的な方法では、直接的な副作用は少ないものの、効果が限定的である点が注意点として挙げられます。
また、和痛分娩では痛みが完全に取り除かれないため、分娩中に痛みに対する不安が強くなる場合があります。このような心理的な負担も考慮して、十分な説明と心理的サポートが必要です。
無痛・和痛分娩は人によって感じ方が異なる
無痛分娩、和痛分娩ともに、効果には個人差があることを理解しておくことが重要です。体質、痛みの感じ方、分娩の進行状況、胎児の位置などによって、期待した効果が得られない場合もあります。そのため、完全に痛みがなくなることを期待するのではなく、痛みの軽減と分娩時のストレス軽減を目的として考えることが大切です。
また、痛み軽減の効果だけでなく、分娩時間の長さや分娩の進行にも影響することがあります。無痛分娩では、陣痛が弱くなることで分娩時間が延長する場合があり、器械分娩が必要になることもあります。これらの点も含めて、医師と十分に相談して選択することが重要です。
病院によって異なる無痛分娩と和痛分娩の定義
注意すべき点として、「無痛分娩」と「和痛分娩」の定義は医療機関によって異なる場合があります。ある病院では硬膜外麻酔を使用した場合でも「和痛分娩」と呼ぶことがあり、別の病院では同じ方法を「無痛分娩」と呼ぶことがあります。そのため、分娩方法を選択する際は、具体的にどのような手法を用いるのかを医師に確認することが重要です。
このような用語の違いが生じる理由は、日本では無痛分娩の普及が比較的新しく、統一された定義が確立されていないためです。実際に医療機関を選ぶ際は、名称だけでなく、具体的な麻酔方法や痛み軽減の程度について詳しく説明を受けることをお勧めします。
無痛分娩に関するよくある質問と回答
無痛分娩を検討する際、多くの方が抱く疑問や不安があります。ここでは、よくある質問とその回答を医学的根拠に基づいて詳しく説明します。
Q. 麻酔による血圧低下が胎児に与える影響はありますか?
A. 硬膜外麻酔を使用する無痛分娩では、お母さんの血圧が一過性に低下することがあります。これは麻酔薬が交感神経をブロックし、血管が拡張することによるものです。血圧低下により、一時的に子宮内の胎児への血流が減少し、胎児の心拍数に変化が生じる可能性があります。
しかし、適切な医学的管理のもとでは、このリスクを最小限に抑えることができます。分娩中は母体の血圧と胎児の心拍数を継続的にモニタリングし、異常が認められた場合は速やかに対処します。血圧低下に対しては、点滴による輸液療法や昇圧薬の投与により改善を図ります。通常、適切な管理が行われれば、血圧低下による胎児への重大な影響は避けることができます。
Q. 無痛分娩が長引いた場合の措置や麻酔調整はありますか?
A. 無痛分娩中に分娩が長引いた場合、麻酔の効果を維持するために追加の麻酔薬投与を行います。硬膜外麻酔では、継続的な麻酔薬の投与が可能で、分娩の進行状況に応じて投与量を調整できます。また、分娩進行の遅延が認められる場合は、微弱陣痛の改善のためにオキシトシンによる陣痛促進が併用されることがあります。
長時間の分娩では、母体の疲労や脱水を防ぐため、適切な水分補給と栄養管理も重要です。麻酔の効果により痛みが軽減されているため、お母さんはより体力を温存できますが、分娩の進行状況によっては吸引分娩や鉗子分娩などの器械分娩が必要になる場合もあります。医師は母体と胎児の状態を総合的に評価し、最適な管理方針を決定します。
Q. 無痛分娩の開始タイミングは子宮口何センチから可能ですか?
A. 無痛分娩の開始タイミングは医療機関によって方針が異なりますが、一般的に陣痛が開始し、子宮口が4〜5cm開大した段階で開始されることが多いです。この時期は分娩が確実に進行していることが確認でき、麻酔による分娩進行への影響を最小限に抑えることができます。
ただし、強い陣痛恐怖症や医学的な理由がある場合は、より早い段階での開始が検討されることもあります。逆に、分娩の進行が急速な場合は、麻酔の効果が十分に発揮される前に分娩が終了してしまう可能性もあります。開始タイミングは、母体の状態、陣痛の強さ、子宮口の開大度、胎児の状態などを総合的に評価して決定されます。計画分娩として陣痛促進剤を使用する場合は、事前に入院し、管理された環境で麻酔を開始することも可能です。
無痛分娩を理解して安心の出産を
無痛分娩と和痛分娩は、分娩時の痛みを軽減する有効な選択肢ですが、それぞれに特徴とリスクがあります。無痛分娩は硬膜外麻酔により強い痛み軽減効果が期待できる一方、血圧低下や胎児への間接的影響などのリスクも存在します。
和痛分娩は自然な分娩により近い状態で痛みを軽減できますが、効果は限定的です。どちらの方法も適切な医学的管理のもとで行われれば、安全性は高いとされています。
最も重要なのは、個人の状況や希望に応じた最適な選択をすることです。医師との十分な相談を通じて、メリットとリスクを理解し、納得のいく分娩方法を選択してください。




