公開日 2025/08/12
安産祈願・戌の日とは?いつ行く?由来・持ち物・服装マナーについて

目次
この記事の監修者
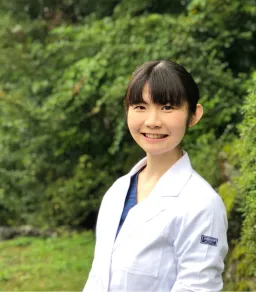
久保田産婦人科病院
西野 枝里菜 先生
妊娠5ヶ月に入ると、多くのパパ・ママが「戌の日の安産祈願」について考え始めるのではないでしょうか。戌の日とは、12日に一度巡ってくる特別な日で、古くから安産祈願を行う吉日として親しまれています。犬は多産で軽いお産をするとされることから、その象徴的な意味が込められているのです。
安産祈願は、妊娠5ヶ月目の最初の戌の日に神社やお寺で行うのが一般的です。しかし、初めての妊娠の場合、いつ、どこで、どのような準備をして参拝すれば良いのか分からず不安を感じる方も多いでしょう。また、体調が優れない時や、戌の日以外でも安産祈願は可能なのか、代理参拝はできるのかなど、様々な疑問が生まれることもあります。
この記事では、戌の日の意味や由来、安産祈願の時期や参拝方法、必要な持ち物や服装マナー、代理参拝の可否などを詳しく解説
戌の日とは?意味や由来について

戌の日は、パパ・ママにとって特別な意味を持つ伝統的な安産祈願の日です。犬の「多産で安産」という特徴にあやかり、古くから大切にされてきました。戌の日の意味や由来を知ることで、祈願に込める気持ちもより深まるでしょう。
戌の日とは?安産祈願と結びついた理由
戌の日とは、十二支の「戌(いぬ)」にあたる日のことで、12日に一度巡ってくる特別な日です。日本では古くから、この戌の日に安産祈願を行う習慣が根付いています。犬は一度に多くの子犬を産み、比較的軽いお産をするとされていることから、安産の象徴として親しまれてきました。
戌の日カレンダーを見ると、毎月2〜3回の戌の日があることが分かります。この日は特に妊娠中の女性やその家族にとって重要な意味を持つ日となっています。現代でも多くの方が、この伝統的な習慣を大切にして安産祈願を行っています。
戌の日の歴史
戌の日の安産祈願は、平安時代から続く古い習慣です。当時の貴族の間で始まったとされ、その後庶民にも広く普及しました。江戸時代には、妊娠5ヶ月目の戌の日に「帯祝い」として腹帯を巻く儀式が一般的になりました。
この習慣は、犬の持つ「多産」「安産」「母性愛の強さ」といった特徴を人間の出産に重ね合わせたものです。また、犬は忠実で家族を守る動物として親しまれており、生まれてくる赤ちゃんを守ってくれるという願いも込められています。
現代における意義
現代の戌の日は、妊娠中の女性とその家族にとって心の支えとなる特別な日です。医学的には安定期に入る妊娠5ヶ月目に行うことで、妊婦さんの精神的な安定にもつながります。また、家族が一丸となって出産を迎える準備をする節目としても重要な意味を持っています。
戌の日の安産祈願は、科学的な根拠よりも、むしろ心理的な効果が大きいとされています。不安を抱えがちな妊娠期間において、神仏に祈ることで心が落ち着き、前向きな気持ちで出産に臨むことができるのです。家族の絆を深め、生まれてくる赤ちゃんへの愛情を確認する機会でもあります。
案産祈願はいつ行う?妊娠5か月目の戌の日が最適
安産祈願を行うベストな時期は妊娠5ヶ月目と言われています。ただし、体調や都合に合わせて無理なく進めることが大切です。
ここでは、戌の日以外の選択肢や体調不良時の対応についてもお伝えします。
妊娠5ヶ月(16〜19週)|胎動がわかる?マタニティライフを楽しむコツと注意点
妊娠5か月目の戌の日に安産祈願を行う理由
安産祈願を行う最適なタイミングは、妊娠5ヶ月目(16週〜19週頃)の最初の戌の日です。この時期は安定期に入った頃で、つわりが落ち着き、体調が比較的安定している時期にあたります。出産予定日の計算から逆算して、妊娠5ヶ月目がいつ頃になるかを確認しておくと良いでしょう。
妊娠5ヶ月目の戌の日を選ぶ理由は、胎児の状態が安定し、流産のリスクが下がる時期とされているからです。この頃になると、お腹の膨らみも目立ち始め、妊娠の実感が湧いてくる時期でもあります。また、体調的にも神社やお寺への参拝が無理なく行える時期として適しています。
2025年の戌の日カレンダー(六曜付き)
六曜は参考程度に。体調や予定に合わせて参拝日を選びましょう。
月 | 曜日 | ||
|---|---|---|---|
1月 | 5日(日)大安 | 17日(金)大安 | 29日(水)先勝 |
2月 | 10日(月)先勝 | 22日(土)先勝 | |
3月 | 6日(木)友引 | 18日(火)友引 | 30日(日)仏滅 |
4月 | 11日(金)仏滅 | 23日(水)仏滅 | |
5月 | 5日(月・祝)大安 | 17日(土)大安 | 29日(木)先勝 |
6月 | 10日(火)先勝 | 22日(日)先勝 | |
7月 | 4日(金)先負 | 16日(水)先負 | 28日(月)先負 |
8月 | 9日(土)先負 | 21日(木)先負 | |
9月 | 2日(火)大安 | 14日(日)大安 | 26日(金)赤口 |
10月 | 8日(水)赤口 | 20日(月)赤口 | |
11月 | 1日(土)友引 | 13日(木)友引 | 25日(火)先負 |
12月 | 7日(日)先負 | 19日(金)先負 | 31日(水)仏滅 |
※2025年版。
戌の日以外に安産祈願をしても大丈夫?
戌の日が最も適しているとされますが、必ずしも戌の日でなければならないわけではありません。体調が優れない場合や、戌の日が平日で都合がつかない場合は、他の日に参拝しても問題ありません。多くの神社やお寺では、戌の日以外でも安産祈願を受け付けています。
大切なのは、パパ・ママが心を込めて祈ることです。戌の日にこだわりすぎて体調を崩したり、無理をしたりするよりも、体調の良い日を選んで参拝することをおすすめします。神社やお寺に事前に確認すれば、戌の日以外でも丁寧に対応してもらえるでしょう。
体調不良で参拝できないときの対応方法
妊娠中は体調が変わりやすいため、当日になって体調が悪くなることもあります。そのような場合は、無理をせず参拝を延期するか、代理参拝を検討しましょう。多くの神社やお寺では、家族による代理参拝を受け付けています。
代理参拝の場合は、事前に神社やお寺に連絡して、代理参拝が可能かどうか確認しておくことが大切です。代理で参拝する方は、妊婦さんの名前で祈祷を受けることになります。後日、体調が回復してからお礼参りに行くこともできますので、無理は禁物です。
安産祈願は神社とお寺どっち?違いと選び方
安産祈願は神社でもお寺でも行うことができます。それぞれの特徴を知り、自分たちに合った場所を選ぶのがポイントです。どちらを選んでも大切なのは、家族で心を込めて祈ることです。
神社で安産祈願を行う流れと特徴
神社での安産祈願は、日本古来の神道に基づいた儀式です。神社では、安産の神様として親しまれている神様に祈りを捧げます。代表的な安産の神様には、木花咲耶姫命(このはなさくやひめのみこと)や、水天宮の神様などがいます。神社での祈祷は、祝詞を奏上し、玉串を奉納する形式が一般的です。
神社での安産祈願は、日本の伝統的な文化を重視する方に特に人気があります。神社によっては、安産祈願専用の特別な祈祷を行っているところもあります。全国各地に安産で有名な神社があるため、住んでいる地域やアクセスの良さを考慮して選ぶと良いでしょう。
お寺で安産祈願を行う流れと特徴
お寺での安産祈願は、仏教の教えに基づいた祈祷です。お寺では、子安観音や鬼子母神などの仏様に安産を祈願します。お寺での祈祷は、読経や護摩焚きなど、神社とは異なる形式で行われることが多いです。仏教の慈悲の心に基づいた、温かい雰囲気の中で祈願できるのが特徴です。
お寺での安産祈願は、仏教を信仰している方や、お寺の厳かな雰囲気を好む方におすすめです。また、お寺によっては、妊婦さんの体調に配慮した特別な配慮をしてくれるところもあります。事前に確認して、自分たちに合った場所を選ぶことが大切です。
安産祈願の神社とお寺の選び方
神社とお寺のどちらを選ぶかは、個人の信仰や好みによって決めて構いません。重要なのは、パパ・ママが心から祈ることができる場所を選ぶことです。地域で有名な安産祈願の神社やお寺があれば、そこを選ぶのも良いでしょう。
選ぶ際のポイントとしては、アクセスの良さ、駐車場の有無、予約の必要性、混雑状況などを考慮しましょう。特に戌の日は混雑することが多いため、事前に予約ができるかどうか確認しておくことをおすすめします。また、妊婦さんの体調を考慮して、あまり遠くない場所を選ぶことも大切です。
安産祈願に必要な持ち物と服装マナー
安心して参拝するためには、必要な持ち物や服装選びも重要です。母子手帳や腹帯など、当日忘れないように準備しましょう。神聖な場所にふさわしい服装を選んで、気持ちよく祈願に臨んでください。
必要な持ち物
安産祈願に行く際の必要な持ち物は、まず母子手帳です。母子手帳は妊娠の証明となるため、必ず持参しましょう。次に、腹帯を持参します。腹帯は神社やお寺で祈祷してもらい、お腹に巻くことで赤ちゃんを守るという意味があります。腹帯の巻き方については、事前に確認しておくか、現地で指導してもらいましょう。
その他の持ち物としては、初穂料(神社の場合)や祈祷料(お寺の場合)を用意します。初穂料の相場は一般的に5,000円から10,000円程度ですが、神社やお寺によって異なるため、事前に確認しておきましょう。また、万が一の時のために保険証も持参しておくと安心です。
持ち物リスト
- 母子手帳:妊娠の証明になる大切なもの
- 腹帯(岩田帯):祈祷してもらい、お腹に巻く習わしがある
- 初穂料・祈祷料:目安は5,000〜10,000円程度(神社・お寺により異なる)
- 保険証:万が一の体調不良に備えて
- 常用薬:服用している薬があれば
など
【医師解説】出産準備はいつから?妊娠期別の準備ポイントと母子手帳・マタニティマークの取得方法について
安産祈願の服装マナー
安産祈願に参拝する際の服装は、神聖な場所にふさわしい格好を心がけましょう。妊婦さんは、お腹を締め付けない楽な服装が基本ですが、あまりにもカジュアルすぎる服装は避けるべきです。ワンピースやブラウスにスカートなど、上品で清楚な印象の服装がおすすめです。
色については、明るすぎる色や派手な柄は避け、落ち着いた色合いを選びましょう。靴は歩きやすく、滑りにくいものを選ぶことが大切です。ヒールの高い靴は転倒の危険があるため避けましょう。家族の方も、神社やお寺にふさわしい服装を心がけることが大切です。
服装のポイント
- 妊婦さんはお腹を締め付けない服
- 清楚で落ち着いた色合い
- 靴は歩きやすく滑りにくいもの
- 家族も神社・お寺にふさわしい服装を意識
など
安産祈願の参拝時に気をつけたいこと
参拝中は、妊婦さんの体調を最優先に考えましょう。正座での祈祷が一般的ですが、正座が辛い場合は遠慮なく神社やお寺の関係者に相談してください。多くの場合、椅子を用意してもらえたり、座り方を変更してもらえたりします。無理をして体調を崩すことのないよう注意しましょう。長時間の祈祷になる場合もあるため、途中で気分が悪くなったら無理をせずに申し出ることが大切です。また、混雑している場合は、人混みで体調を崩さないよう注意が必要です。家族の方は、妊婦さんの様子を常に気にかけ、サポートすることを心がけましょう。
安産祈願の準備と当日の流れ
安産祈願を安心して行うためには、事前の準備や当日の流れを知っておくことが大切です。ここでは、神社やお寺での安産祈願の基本的な参拝方法を紹介します。大切な一日を心穏やかに過ごすための参考にしてください。
安産祈願に行く前の準備
安産祈願に行く前に、まず神社やお寺に連絡を取って、祈祷の予約が必要かどうか確認しましょう。特に戌の日は混雑することが多いため、予約ができる場合は事前に予約を取ることをおすすめします。予約の際に、初穂料や祈祷料の金額、所要時間、持ち物なども確認しておきましょう。
また、当日のスケジュールも余裕を持って計画しましょう。妊婦さんの体調を考慮し、無理のない時間帯を選ぶことが大切です。午前中の比較的涼しい時間帯や、混雑を避けた時間帯を選ぶと良いでしょう。交通手段についても、電車やバスよりも車での移動が楽な場合が多いです。
【医師解説】妊娠中に食べたほうが良いもの・食べられないものは?気持ち悪いつわり中でも食べられる食べ物は?
安産祈願当日の流れ
参拝当日は、まず受付で安産祈願の申し込みを行います。この時に、妊婦さんの名前や住所、出産予定日などを記入します。初穂料や祈祷料もこの時に納めます。受付が済んだら、祈祷が始まるまで待機します。神社やお寺によっては、待合室が用意されている場合もあります。
祈祷が始まったら、指定された場所に座ります。神社では祝詞の奏上、お寺では読経が行われます。祈祷の時間は通常20分から30分程度です。祈祷が終わったら、お守りや御札をいただきます。これらは大切に持ち帰り、出産まで身につけたり、自宅に飾ったりします。
安産祈願後の過ごし方とお守りの扱い
祈祷が終わった後は、お守りの種類や効果について説明を受けることもあります。安産祈願のお守りには、様々な種類があり、それぞれに特別な意味が込められています。お守りは妊婦さんが身につけるものと、自宅に飾るものとがあります。正しい使い方を教えてもらいましょう。
参拝の後は、無理をせずにゆっくりと帰路につきましょう。可能であれば、近くで軽食を取ったり、休憩したりすることをおすすめします。この日は特別な日として、家族で過ごす時間を大切にしましょう。写真を撮ったり、日記に記録したりして、思い出に残すのも良いでしょう。
安産祈願は誰と行く?家族参拝と代理参拝
安産祈願は家族みんなで赤ちゃんの誕生を願う大切な機会です。体調が優れない場合には代理参拝という方法もあります。安心して祈願を行うために、家族でのサポート体制を考えておきましょう。
安産祈願は誰と行くべき?
安産祈願には、妊婦さんだけでなく、家族で参拝することが一般的です。特に、パートナーと一緒に参拝することで、夫婦の絆を深め、共に出産を迎える準備をすることができます。また、両親や義両親と一緒に参拝する場合もあります。家族全員で赤ちゃんの誕生を祈ることで、家族の結束が強まります。
誰と行くかは、各家庭の事情や関係性によって決めれば良いでしょう。大切なのは、心から祈ることができる人たちと一緒に参拝することです。人数が多くなりすぎると、妊婦さんの負担になることもあるため、適度な人数で参拝することをおすすめします。
代理参拝の方法と流れ
妊婦さんの体調が優れない場合や、流早産などで安静が必要な場合は、代理参拝を検討しましょう。代理参拝は、家族の方が妊婦さんの代わりに参拝することです。多くの神社やお寺では、代理参拝を受け付けています。事前に連絡して、代理参拝が可能かどうか確認しておきましょう。
代理参拝の場合は、妊婦さんの名前で祈祷を受けることになります。代理で参拝する方は、妊婦さんの状況や出産予定日などを正確に伝える必要があります。また、妊婦さんの気持ちを代弁して、心を込めて祈ることが大切です。後日、体調が回復してからお礼参りに行くこともできます。
代理参拝の注意点
代理参拝を行う場合は、妊婦さんの体調や状況について、正確に神社やお寺に伝えることが重要です。また、代理参拝であることを最初に伝えて、適切な祈祷を受けるようにしましょう。代理参拝でも、通常の祈祷と同じように丁寧に行ってもらえます。
代理参拝の際に受け取ったお守りや御札は、大切に妊婦さんに渡しましょう。また、祈祷の様子や神社・お寺の雰囲気なども、後で妊婦さんに伝えてあげると良いでしょう。代理参拝でも、祈りの気持ちは十分に伝わります。無理をしないことが、母子の健康にとって最も大切です。
安産祈願・戌の日に関するよくある質問と回答
安産祈願について、多くのパパ・ママが疑問に思うことがあります。ここでは、よくある質問とその回答をご紹介します。これらの情報を参考に、安心して安産祈願に臨んでください。
Q. 戌の日以外でも神社やお寺は安産祈願を受け付けてくれますか?
A. はい、多くの神社やお寺では戌の日以外でも安産祈願を受け付けています。戌の日は伝統的に最も適した日とされていますが、体調や都合により他の日を選んでも全く問題ありません。大切なのは、パパ・ママが心を込めて祈ることです。事前に神社やお寺に連絡すれば、戌の日以外でも丁寧に対応してもらえるでしょう。
また、戌の日に比べて混雑が少ないため、じっくりと祈祷を受けることができるというメリットもあります。神社やお寺の関係者の方も、妊婦さんの体調を最優先に考えて対応してくれますので、安心して相談してください。
Q. 安産祈願の参拝中に体調が悪くなった場合、あると安心な持ち物は?
A. 安産祈願の参拝に必要な持ち物として、まず 母子手帳と腹帯 は必須です。これに加えて、万が一に備えて 保険証 を必ず持参しましょう。普段服用している薬があれば忘れずに持参してください。妊娠中は体調が変わりやすいため、水分を多めに準備しておくと安心です。
さらに「あると便利な持ち物」として、小さなクッションやひざ掛けがあると長時間の祈祷も楽に過ごせます。緊急時に備えて、かかりつけの産婦人科の連絡先をメモしておくのもおすすめです。
これらを準備しておけば、安産祈願の参拝中も安心して過ごすことができます。
Q. 妊娠中でも安産祈願は正座で受けなければいけませんか?
A. 安産祈願は、ほとんどの神社やお寺で椅子に座って受けられるのが一般的です。正座が必須ということはほとんどありません。妊婦さんの体調に配慮して椅子を用意してくれる場合が多く、事前に相談しておけば安心です。
もし畳の上での祈祷などで正座を求められる場合でも、辛ければ無理をせず、あぐらや横座りなど楽な姿勢で参拝して問題ありません。大切なのは形式ではなく、妊婦さんの体調と安全です。神社やお寺の方も健康を第一に考えてくれるので、遠慮なく相談してください。
妊婦さんの体調と安全を最優先に安産祈願を
安産祈願は、妊娠5ヶ月目の戌の日に行う伝統的な習慣ですが、最も大切なのは妊婦さんの体調と安全です。戌の日の意味を理解し、適切な準備をして参拝することで、心の支えとなる大切な体験となるでしょう。
神社やお寺の選択、持ち物の準備、服装マナーなど、事前にしっかりと確認しておくことで、安心して参拝することができます。体調が優れない場合は、代理参拝という選択肢もあることを覚えておきましょう。
パパ・ママが心を込めて祈ることで、家族の絆が深まり、出産への前向きな気持ちを育むことができます。安産祈願を通じて、生まれてくる赤ちゃんを迎える準備を整え、穏やかな気持ちで出産の日を迎えてください。




