公開日 2025/08/12
【医師解説】出産準備はいつから?妊娠期別の準備ポイントと母子手帳・マタニティマークの取得方法について
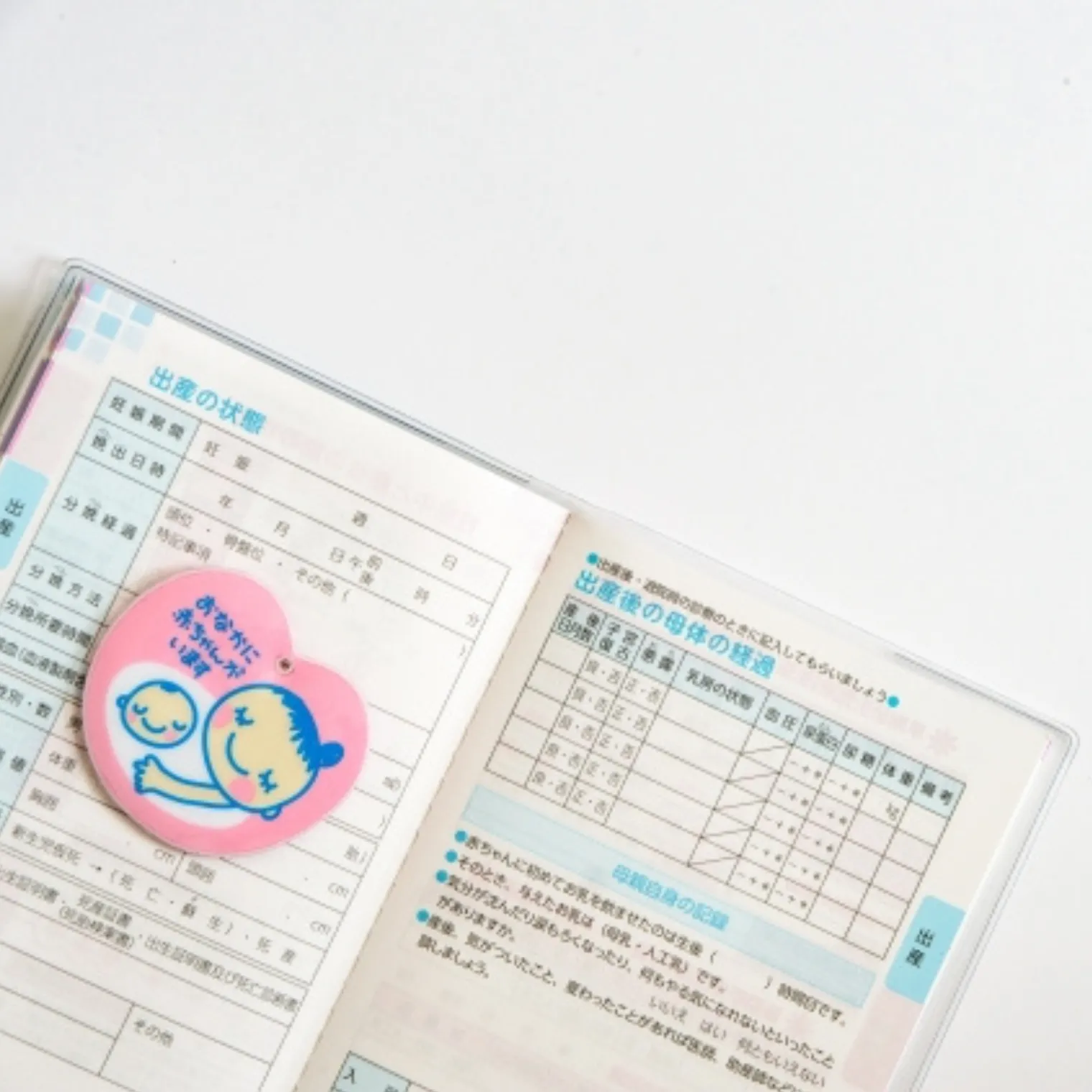
目次
この記事の監修者
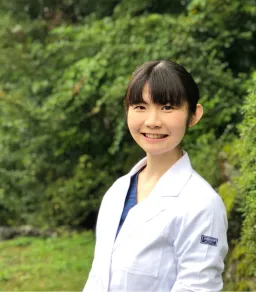
久保田産婦人科病院
西野 枝里菜 先生
初めての妊娠では「出産準備はいつから?何をすればいいの?」と不安になる方も多いでしょう。母子手帳やマタニティマークの取得、母親学級の参加時期など、気になる手続きも少なくありません。
産婦人科医として多くの妊婦さんを見てきた経験から、本記事では妊娠初期・中期・後期ごとに必要な準備や手続きをわかりやすく解説します。
出産準備はいつから始める?
出産準備は妊娠がわかったその日から少しずつ始まります。とはいえ、一度にすべてを揃える必要はありません。妊娠初期・中期・後期と進むにつれて体調や生活も変化するため、時期に合わせて準備を進めるのが安心です。
妊娠初期は母子手帳やマタニティマークの取得など手続きが中心、中期は体調が安定するので本格的な準備に取りかかり、後期は出産直前に必要な入院グッズやベビー用品を整える時期となります。
優先すべき準備を時期ごとに整理しておくと、余裕を持って計画的に備えることができます。
妊娠初期(妊娠2~13週)の出産準備について
妊娠初期は体調が不安定になりやすい時期ですが、重要な手続きや準備を始める時期でもあります。
この時期に最優先で行うべきことは、母子手帳の取得と出産病院選びです。
妊娠判明後、まずは産婦人科を受診して妊娠確定の診断を受けます。心拍確認ができた段階で、市区町村役場で妊娠届出書を提出し、母子手帳を受け取りましょう。その際に健康保険証とマイナンバーカードの持参が必要です。
この時期には、つわりなどの体調変化に対応するための準備も必要です。
マタニティマークを取得して、公共交通機関で周囲から配慮を受けられるようにしておきましょう。また、胎児神経管閉鎖障害を予防するために、葉酸サプリメントを飲み始めましょう。
母子手帳の取得方法とタイミングについて
母子手帳は妊娠中から育児期間中まで長期間使用する重要な書類です。取得方法と必要書類について詳しく説明します。
母子手帳はいつもらえる?
母子手帳は、産婦人科で妊娠確定の診断を受けた後、心拍確認ができた段階で取得するのが一般的です。妊娠6~8週頃が目安となります。
早すぎる取得は、万が一の場合に手続きが複雑になることがあるため、医師から「母子手帳をもらってきてください」と言われてから取得することをお勧めします。
取得後は、妊婦健診の際に必ず持参するようにしましょう。健診結果や妊娠経過の記録、予防接種の履歴など、重要な情報が記載されます。
母子手帳はどこでもらえる?
母子手帳の取得には、妊娠届出書の提出が必要です。妊娠届出書は市区町村役場の窓口で配布されていますが、事前にホームページからダウンロードすることも可能です。
持参する書類は、健康保険証、マイナンバーカード(または通知カード)、印鑑(シャチハタ不可)です。場合によっては、産婦人科からの妊娠証明書が必要な自治体もあるため、事前に確認しておきましょう。
手続きは平日の開庁時間内に行う必要があります。窓口での待ち時間を考慮して、時間に余裕を持って訪問することをお勧めします。
母子手帳の役割
母子手帳は、妊娠中の健康管理記録から子どもの成長記録まで、長期間にわたって使用する重要な書類です。妊婦健診の結果や予防接種の記録、子どもの発育状況などが記載されます。
また、妊娠中の体調変化や気になることを記録するページもあるため、日記代わりに活用することもできます。医師との相談時にも、過去の記録を参考にしながら適切なアドバイスを受けられます。
転居する場合でも、母子手帳は全国共通で使用できるため、引っ越し先でも継続して使用できます。紛失しないよう大切に保管しましょう。
マタニティマークの取得方法について

マタニティマークは妊婦さんの安全と健康を守るための重要なアイテムです。取得方法や活用法について詳しく説明します。
市区町村役場でもらう
最も一般的な取得方法は、市区町村役場で母子手帳を受け取る際に一緒にもらう方法です。妊娠届出書を提出して母子手帳交付を受ける時に、マタニティマークも同時に配布されることが多いです。
自治体によっては、地域オリジナルデザインのマタニティマークを配布している場合もあります。デザインにこだわりがある場合は、事前に自治体のホームページで確認しておくとよいでしょう。
窓口での手続きの際は、健康保険証とマイナンバーカードを持参することを忘れずに。担当者から妊娠中の健康管理や育児支援についての説明も受けられるため、疑問があれば積極的に質問しましょう。
鉄道会社や交通機関でもらう
多くの鉄道会社では、駅の窓口やサービスセンターでマタニティマークを配布しています。JRや私鉄の主要駅では、無料で配布されていることが多いです。
ただし、駅によっては在庫がない場合もあります。また、配布時間が限られている場合もあるので、営業時間内に訪問するよう注意しましょう。
公共交通機関での配布は、妊婦さんの移動時の安全確保を目的としているため、電車やバスを利用する機会が多い方にとって特に便利です。
ベビー用品店や産婦人科でもらう
ベビー用品店では、会員登録特典としてマタニティマークを配布している場合があります。サンプルセットに同梱されていることもあるので、店舗で確認してみましょう。
産婦人科や助産院でも、妊婦さん向けサービスの一環としてマタニティマークを配布している場合があります。定期健診の際に、担当医師や助産師に確認してみることをお勧めします。
これらの場所では、妊娠中の体調管理に関するアドバイスも同時に受けられるため、マタニティマーク取得と合わせて相談してみるとよいでしょう。
妊娠初期症状はいつから出る?チェックポイントや診断方法について
妊娠中期(妊娠14~27週)の出産準備について

妊娠中期は比較的体調が安定する時期で、本格的な出産準備を始める最適なタイミングです。安定期に入ったら、母親学級への参加申し込みを検討しましょう。
この時期には、妊娠中の健康管理に必要なアイテムの準備も始めます。マタニティウェアや妊娠線予防クリームなど、妊娠中の体調管理をサポートするアイテムを揃えていきます。
また、出産費用の準備も重要な項目です。出産育児一時金の手続きについて確認し、必要な書類を準備しておきましょう。
母親学級とは?参加時期や内容について
母親学級は妊娠・出産・育児について学べる貴重な機会です。参加時期や内容について詳しく説明します。
母親学級はいつから参加する?
母親学級への参加は、一般的に妊娠中期以降から可能です。安定期に入った妊娠16週頃から参加申し込みができる場合が多いです。
最適な参加時期は妊娠20~32週頃とされています。この時期は体調が比較的安定しており、出産に向けて具体的な準備を始める時期でもあります。
臨月に近づくと体調面での負担も大きくなるため、妊娠30週頃までには参加を完了させておくことをお勧めします。
母親学級の種類
母親学級には、市区町村主催、病院主催、民間教室の3つの種類があります。市区町村主催の教室は無料または低価格で参加でき、基本的な妊娠・出産・育児の知識を学べます。
病院主催の教室は、その病院で出産予定の妊婦さんを対象としており、病院の方針や設備について詳しく説明を受けられます。出産準備リストの作成や陣痛時の対応方法なども学べます。
民間教室では、より専門的な内容やオリジナルのプログラムを受講できる場合があります。費用は高めですが、個別対応や充実したサポートを受けられることが多いです。
申し込み方法
市区町村主催の母親学級は、役場の窓口や電話、インターネットで申し込めます。定員制の場合が多いため、早めの申し込みがお勧めです。
病院主催の教室は、妊婦健診の際に申し込み方法を確認しましょう。予約制の場合が多く、人気の時間帯は早めに埋まってしまうことがあります。
参加の際は、母子手帳と筆記用具を持参しましょう。また、体調に不安がある場合は、事前に医師に相談してから参加することが大切です。
出産準備費用の目安について
出産準備には様々な費用がかかります。計画的に準備を進めるための費用の目安と節約方法について説明します。
出産準備にかかる費用の総額は、平均的に10万円から20万円程度とされています。ただし、選ぶアイテムや購入場所によって大きく変わるため、予算に応じて調整することが大切です。
最低限必要なアイテムのみを揃える場合でも、7万円から10万円程度は見積もっておくことをお勧めします。これには、マタニティウェア、入院グッズ、ベビー用品の基本的なアイテムが含まれます。
出産費用は別途必要になるため、出産育児一時金の支給額と自己負担額を事前に確認しておきましょう。
出産準備の費用を抑える方法として、まずは必要最低限のアイテムから揃えることが大切です。産後に必要になってから追加購入する方法もあります。
中古品の活用も効果的な節約方法です。ベビー用品の中古品は、短期間しか使用されないため状態が良いものが多く、リサイクルショップやフリマアプリで購入できます。
また、親戚や友人からのお下がりを活用することも考えてみましょう。特にベビー服は成長が早いため、お下がりでも十分に活用できます。
妊娠後期(妊娠28週以降)の出産準備について
妊娠後期になると、いよいよ出産が近づいてきます。この時期には、出産時に必要な入院グッズや産後すぐに使うベビー用品を準備しましょう。
陣痛バッグや入院バッグの準備は、妊娠35週頃までには完了させておくことをお勧めします。突然の陣痛に備えて、必要なものをすぐに持ち出せるよう準備しておくことが大切です。
産後手続きについても事前に確認しておきましょう。出生届の提出方法や育児手当の申請手続きなど、産後に必要な手続きを把握しておくことで、慌てずに対応できます。
妊娠後期はいつから始まる?妊娠後期に避けた方がいいこととは?
出産後費用の手続きについて
出産後には、出産育児一時金の申請や育児手当の手続きが必要です。これらの手続きは産後手続きの一部として、早めに済ませておくことが大切です。
児童手当の申請も忘れずに行いましょう。出生届の提出と同時に申請することで、手続きを効率的に進められます。
健康保険の扶養手続きも重要です。赤ちゃんの健康保険証を早めに取得することで、1か月健診や予防接種の際に安心して受診できます。
出産の兆候!おしるしの量や色・前駆陣痛・破水とは?対処法まで解説
陣痛の間隔はどれくらい?どんな痛み?前駆陣痛と本陣痛の違いまで詳しく解説
里帰り出産はいつから準備する?
里帰り出産を予定している場合は、通常の出産準備に加えて特別な準備が必要です。スムーズな里帰り出産のためのポイントを説明します。
里帰り出産の準備スケジュール
里帰り出産の場合、妊娠34週頃までには里帰り先の病院での初診を受けることが一般的です。それまでに、現在通院している病院からの紹介状や検査結果を準備しておきましょう。
里帰り先での母親学級への参加も考慮に入れましょう。里帰り先の自治体や病院主催の教室に参加することで、出産予定の病院の方針や地域の育児支援について理解を深められます。
交通手段の確保も重要です。妊娠後期の移動は体への負担が大きいため、無理のない移動方法を選択しましょう。
里帰り出産に必要な書類
里帰り出産の際は、母子手帳や健康保険証、妊婦健診の助成券などの必要書類を忘れずに持参しましょう。これらの書類は、里帰り先での健診や出産時に必要になります。
現在通院している病院から、里帰り先の病院への紹介状を作成してもらうことも大切です。妊娠経過や検査結果などの重要な情報が記載されているため、継続的な医療を受けるために必要です。
出産後の手続きについても、里帰り先での対応について事前に確認しておきましょう。出生届の提出場所や児童手当の申請方法など、地域による違いを把握しておくことが大切です。
里帰り先での生活準備
里帰り先での生活に必要なマタニティウェアや入院グッズを準備しましょう。荷物を最小限に抑えるために、現地で購入できるものと持参すべきものを分けて考えることが大切です。
産後の生活に必要なベビー用品についても、里帰り先で準備するか持参するかを決めておきましょう。特に、退院時に必要な赤ちゃんの服やおむつなどは、事前に準備しておくことをお勧めします。
家族との連絡体制も整えておきましょう。陣痛が始まった際の連絡方法や、産後の面会スケジュールなどを事前に相談しておくことで、スムーズな出産を迎えられます。
出産準備に関するよくある質問と回答
出産準備について、多くの妊婦さんから寄せられるよくある質問にお答えします。これらの情報を参考に、不安を解消して安心して出産準備を進めてください。
Q. 里帰り先での母親学級参加は可能ですか?
A. 多くの場合、里帰り先の自治体や医療機関主催の母親学級への参加が可能です。市区町村主催の教室は住民以外でも参加できる場合が多く、病院主催の教室も出産予定がある場合は参加を受け入れてくれることがあります。ただし、定員制限がある場合や、申し込み時期が決まっている場合もあるため、里帰りが決まったら早めに問い合わせることが重要です。里帰り先での参加により、出産予定の病院の方針や地域の育児支援について詳しく知ることができるため、積極的に参加を検討することをお勧めします。
Q. パートナーが参加できる母親学級や両親学級はありますか?
A. 最近では、パートナーも一緒に参加できる両親学級が増加しています。市区町村主催の教室では、土日に両親学級を開催している場合が多く、働いているパパも参加しやすい環境が整っています。病院主催の教室でも、平日夜間や休日に夫婦で参加できるプログラムを用意している場合があります。両親学級では、妊娠中のパートナーへのサポート方法や沐浴の実践、育児の分担について学ぶことができます。ただし、開催日時や曜日が限定されている場合もあるため、事前に詳細を確認して早めに申し込むことが大切です。
Q. 出産準備にかかる費用総額はどれくらいですか?
A. 出産準備の費用総額は、平均的に10万円から20万円程度ですが、選択するアイテムや購入場所によって大きく変わります。最低限必要なアイテムのみを揃える場合でも、約7万円から10万円程度は見積もっておくことをお勧めします。費用を抑えるには、必要最低限のアイテムから揃え始め、産後に必要になってから追加購入する方法があります。中古品の活用やお下がりの利用も効果的な節約方法です。また、ベビー用品の中には出産後に実際に使ってみてから購入を検討した方が良いものもあるため、急いで全てを揃える必要はありません。予算に応じて計画的に準備を進めることが大切です。
計画的な出産準備で不安解消しよう
出産準備は妊娠判明後から段階的に進めることで、無理なく安心して出産を迎えることができます。マタニティマークや母子手帳の取得、母親学級への参加など、それぞれに適切な時期があることを理解し、計画的に準備を進めましょう。
マタニティマークは市区町村役場、鉄道会社、ベビー用品店など複数の場所で取得できます。母子手帳は妊娠確定後、心拍確認ができた段階で取得し、妊娠中から育児期間中まで大切に活用してください。
母親学級は妊娠中期以降から参加でき、出産や育児について学べる貴重な機会です。パートナーと一緒に参加できる両親学級も増えているため、夫婦で協力して出産準備を進めることをお勧めします。費用面では10万円から20万円程度を目安に、必要最低限のアイテムから揃えて節約を心がけましょう。




