公開日 2024/12/27
【医師解説】赤ちゃんのミルクはいつまで飲ませればいい?やめる卒乳タイミングやフォローアップミルクについて

目次
この記事の監修者

武田 賢大 先生
赤ちゃんにミルクを与えるのはいつまでが適切なのでしょうか。ミルクは赤ちゃんの健やかな成長に欠かせない栄養源ですが、離乳食が進むにつれて徐々に卒業していく必要があります。
本記事では、赤ちゃんへのミルクの与え方や卒業のタイミング、フォローアップミルクの適切な活用法について詳しく解説します。赤ちゃんの成長や発達に合わせた適切な食事の移行を知っておけば、無理なく自然にミルクから卒業させることができるでしょう。
赤ちゃんにミルクを飲ませる期間はいつまで?卒乳のタイミング
はじめに、赤ちゃんがいつまでミルクを飲むものなのか、その目安となる時期や基準、そして離乳食の進展に合わせてミルクから卒業していく流れについてわかりやすく解説します。
母乳とミルクの違いは?
赤ちゃんの栄養源には、主に母乳とミルク(人工乳)があり、それぞれ特性があります。母乳はママの免疫成分や最適な栄養バランスを含み、赤ちゃんの免疫力向上や情緒的なつながりに役立ちます。一方、ミルクは母乳を参考に栄養を調整しているため、母乳が十分に与えられない場合や、ママが仕事復帰するなどの理由で時間的な制約がある時に便利です。
また、ミルクは誰が与えても量と濃度が一定で、パパやほかの家族も育児に参加しやすい点が魅力です。状況に応じて母乳とミルクを組み合わせることで、赤ちゃんの栄養を確保しながら、家族全体で子育てを分担しやすくなります。大切なのは、赤ちゃんにとって安心で安定した哺乳環境を整えることです。
赤ちゃん(新生児)の吐き戻しはいつまで続く?原因や対処法について
ミルクを飲ませる期間の目安とは?
一般的には、生後5〜6ヶ月頃までは特別な理由がない場合には栄養を母乳やミルクから得ることが望ましいです。この頃までに十分な体重増加が確認でき、首がすわり、よだれが増えて食べ物に興味を示し始めたら、離乳食をスタートさせる目安となります。その後、離乳食の回数が増え、赤ちゃんがさまざまな食材を口にできるようになると、徐々にミルクは補助的な役割にシフトします。1歳前後には、多くの赤ちゃんが食事から主要な栄養素を得るようになり、ミルクは少しずつ卒業の方向へ向かいます。
離乳食の進み具合に合わせてミルクを減らすコツ
離乳食が1日3回程度になり、主食・主菜・副菜のバランスが整い始めたら、ミルクの回数を徐々に減らすタイミングです。たとえば、朝・昼・夕の食事が安定してきたら、これまで1日3〜4回与えていたミルクを2回、最終的に1回へと少しずつ減らしてみましょう。急にミルクをやめると赤ちゃんの戸惑いや栄養面の不安が生じることがあるため、2週間単位など、ゆっくりとしたペースで進めるのがおすすめです。この時、赤ちゃんが空腹で不機嫌にならないよう、離乳食の量や種類を工夫することがポイントです。食事全体の量や栄養価を見直したり、噛みやすい食材ややわらかい食感のものを取り入れることで、赤ちゃんの食欲を引き出しやすくなります。
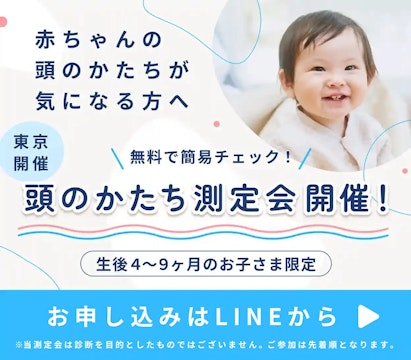
ミルクの卒乳までの手順とポイント

ここでは、具体的にどのようにミルクを減らしていくか、そのステップをわかりやすく解説します。ミルクを減らす際の時間配分や、代替手段としてのコップ飲み練習、夜間授乳の整理、そして離乳食の質的な見直しといった、段階的なミルクを減らすためのコツも紹介しています。
徐々にミルクの量と回数を減らす方法
ミルクの量と回数を減らすには、ゆるやかなステップダウンが基本です。まず、1日あたりのミルクの回数を1回ずつ減らしてみます。たとえば、ミルクが3回ならば昼間の1回をお茶や水分補給に切り替える、翌月には夕方のミルクを少し減らす、といった手順です。重要なのは、赤ちゃんが無理なく適応できるリズムを作ることです。数日おきに赤ちゃんの様子を観察し、機嫌・便通・睡眠リズムが乱れていないか確認しながら進めると安心です。あせらず少しずつ、時間をかけることで赤ちゃんは自然にミルク離れへと向かいます。
マグカップやコップでの飲み方の練習
ミルクを減らしていくにあたって、飲み物を飲むときに使うものを哺乳瓶からマグカップやコップに移していくことも大切です。初めは扱いやすいマグカップを選び、麦茶や白湯などを少量入れ、赤ちゃんが自分で持つ練習をサポートしましょう。こぼしても怒らず、楽しみながら経験を積むことで、「飲む」動作に自立心が芽生えます。慣れてきたら、少しずつ飲み物の種類を増やし、1歳を過ぎた頃を目安に冷たい水や牛乳へと広げていくとよいでしょう。コップ飲みができれば、哺乳瓶へ頼らない習慣が身につき、ミルクからのステップアップがより自然な流れになります。
夜間のミルク授乳をやめるための工夫
夜間の授乳は、ミルクを止めていくための大きなステップです。夜中に目覚めてミルクを欲しがる場合、まずお茶に切り替えて水分補給をしたり、添い寝で安心させたり、絵本を読んで寝かしつけるなど、ミルク以外の方法で落ち着かせる工夫をしましょう。最初は戸惑いがあるかもしれませんが、徐々にミルク以外の安心材料を増やすことで、赤ちゃんは「ミルクがなくても安心して眠れる」ことを学びます。夜間授乳が減ればママやパパの睡眠時間も増え、家族全体の生活リズムが整いやすくなります。
赤ちゃんの夜泣きはいつからいつまで?原因と乗り越えるための対策を解説
離乳食の内容を見直して栄養バランスを整える
ミルクが減るにつれ、赤ちゃんにとって離乳食から必要な栄養をしっかり摂ることがますます重要になります。鉄分・カルシウム・良質なたんぱく質などの不足に注意し、肉・魚・大豆製品・野菜・果物など多彩な食材を活用しましょう。加熱方法や刻み方を工夫して食べやすくするほか、和え物やスープなどで味付けにバリエーションを持たせてあげると、赤ちゃんが気に入る料理が見つかりやすくなります。
ミルクから離れた後のフォローアップミルクの活用法
ここでは、ミルクから離れ始めた後に、耳にすることがある活躍するフォローアップミルクについてや、与え方のポイントについて解説します。フォローアップミルクの使用については、その特徴や位置付けをよく理解することが必要です。離乳食での栄養補完としてフォローアップミルクを上手に取り入れることができれば、食事の質を高めることができるかもしれません。
フォローアップミルクへの切り替え時期や役割とは?

フォローアップミルクは元々牛乳の代用品で作られたものです。牛乳で不足しやすい鉄と、その他補助的にカルシウム、ビタミンを摂取できるように調整されており、厳密には乳児用ミルクとは別の商品です。乳児用ミルクは、赤ちゃんのため成長のために栄養バランスが整えられた完全食として作られているのに対して、フォローアップミルクは補助食品的な位置付けになります。「フォローアップミルク=普通のミルクの上位互換」ではないので注意しましょう。一般的にフォローアップミルクの使用を検討するとされるのは生後9ヶ月頃から1歳頃とされていますが、離乳食がしっかり進み、多様な食材を食べられる場合には、フォローアップミルクは必要ありません。逆に離乳食がうまく進んでいない時は、フォローアップミルクが限定的に役に立つ場合があるかもしれませんが、基本的に栄養バランスの観点から、離乳食の不足分は母乳や乳児用ミルクを与えることが望ましいです。フォローアップミルクの有用性として鉄の補給が謳われますが、離乳食を進めている時期のお子さんの鉄補給の観点でも、離乳食と母乳または乳児用ミルクの組み合わせで問題ないです。もし離乳食がうまく進まない場合には、フォローアップミルクを独自に始めるのではなく、小児科医や保健師などに相談してみましょう。
フォローアップミルクが適している使い方としては、離乳食を進めている段階では、通常のミルクと併用する、鉄分の入った食材が苦手なお子さんの離乳食の材料として、牛乳の代わりに使うなどです。離乳が完了後は、十分に食事が取れているけれど、貧血があり鉄分不足が心配な時に牛乳の代用として役立ちます。フォローアップミルクは有用なタイミングが非常に限定的であくまでサポート役であり、導入の仕方によっては離乳食の進みを悪くすることがあります。メインはあくまで母乳やミルクを使用しながら離乳食を軸とした食生活に移行していくことが大切です。
フォローアップミルクの選び方は?
選ぶ際は、対象月齢や栄養成分表示、味や溶けやすさなどを確認し、赤ちゃんの好みに合いそうなものを選んであげましょう。粉タイプは経済的ですが調乳が必要、液体タイプは手軽さが魅力、といった違いがあるので、生活スタイルや外出のタイミングを考慮して決めると良いでしょう。与える際は、ミルクと同様に適温にして哺乳瓶やマグカップ、コップで少量からスタートします。慣れてくれば、離乳食後のおやつタイムや就寝前の軽い水分・栄養補給として取り入れることもできます。ただし、フォローアップミルクに頼りすぎず、赤ちゃんが食事を通じて栄養を摂取できるように意識することも大切です。
離乳食と組み合わせた栄養管理のポイント
フォローアップミルクは、うまく使用すれば離乳食で不足しがちな鉄分やカルシウムを補う助けになります。まだ食べられる食材が限られている時期にうまく活用すると心強いです。同時に、離乳食そのものも少しずつステップアップしましょう。緑黄色野菜や果物、魚・肉など多彩な食材を組み合わせることで、噛む力や味覚の発達を促します。フォローアップミルクは、あくまで離乳食を支える後方支援的な存在であり、最終的には普通の食事から栄養をしっかり摂れるように導いていくのが目標です。

ミルクの切り替えや牛乳に関するよくある質問
赤ちゃんの成長とともに、ミルクから離乳食への移行や牛乳への切り替えについて気になる疑問をQA形式でご紹介。ぜひ参考にしてください。
Q. 夜間のミルクはいつ頃まで必要でしょうか?
A. 一般的には生後3ヶ月頃までは夜間の授乳が必要ですが、その後は夕ご飯の時間に哺乳をしたら夜間の授乳が空くことが増えてきます。お子さんのペースに合わせて徐々に夜間のミルクを減らし、離乳食が進んだら夜間の水分補給は麦茶や湯冷ましに切り替えるのがよいでしょう。
Q. 牛乳はいつごろから飲ませても大丈夫でしょうか?
A. 離乳食で充分量牛乳が摂取できているのであれば生後1歳を過ぎたら、牛乳を飲料として摂取可能です。粉ミルクからの離脱は、離乳食の回数に合わせて段階的に行い、マグカップなどを活用しながら水分補給の練習をするのがよいでしょう。就寝前のミルクはむし歯のリスクを避けるため、早めに中止することをおすすめします。離乳食の工夫と味付けの工夫で食べやすくすることも大切です。赤ちゃんの発育状況に合わせて柔軟に対応し、ストレスの少ない自然な移行を心がけるとともに、パパ・ママの健康状態とも両立させることが何より重要です。
ミルクの卒業は赤ちゃんのペースに合わせた無理のないステップで
ミルクは、出生直後から成長初期にかけて欠かせない栄養源ですが、離乳食の進行に伴って、徐々に卒業していくのが自然な流れです。大切なのは、赤ちゃんの発育段階に合わせてタイミングを見極め、焦らずゆっくり進めることです。哺乳瓶からマグカップやコップへの移行、夜間のミルク依存をやめる工夫など、段階を踏みながら卒業を進めていきます。不安や疑問を感じたときは、遠慮せずに医療や保健の専門家に相談しましょう。ミルクの卒業は、赤ちゃんがしっかり食事から栄養を取り、健やかに育つ基盤となる大切な発育家庭です。しっかりと見守ってあげましょう。





