公開日 2025/05/19
【医師解説】妊娠6ヶ月(20〜23週)|お腹の張りや体重管理に注意!赤ちゃんとママの今

目次
この記事の監修者
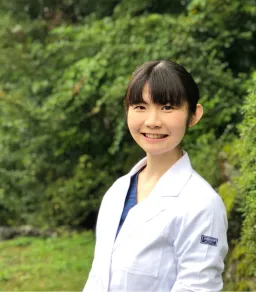
久保田産婦人科病院
西野 枝里菜 先生
妊娠6ヶ月に入ると、いよいよ妊娠中期の真ん中となります。つわりの症状が落ち着き、少しずつ体調が良くなってくる時期です。お腹も目立ち始め、胎動をはっきりと感じられるようになります。この時期は赤ちゃんの器官形成が進み、ママの体も大きく変化していきます。妊娠6ヶ月(20〜23週)の赤ちゃんの成長やママの体の変化、この時期に気をつけるべきポイントについて詳しく解説します。
妊娠6ヶ月目【妊娠20〜23週】の赤ちゃんはどんな成長をする?
妊娠6ヶ月に入ると、赤ちゃんの成長はさらに加速します。週数ごとの発達には個人差がありますが、この時期の赤ちゃんはどのように成長していくのでしょうか。週数別の赤ちゃんの発達について見ていきましょう。
妊娠20週の赤ちゃんの様子
妊娠20週になると、赤ちゃんの身長は約25cm、体重は約300g程度に成長しています。この頃になると、赤ちゃんの運動が盛んになり、手足を動かしたり、体を回転させたりとさまざまな動きができるようになります。
また、腎臓の機能が整い始め、羊水を飲み込んでおしっこをすることができるようになります。味覚や聴覚も発達し、外の音も少しずつ聞こえ始めているのです。お母さんのお腹の外から話しかけると、反応することもあります。この頃になると、超音波検査で赤ちゃんの性別も確認できることが多いです。
さらに、この時期から赤ちゃんは睡眠と覚醒のリズムが形成され始めます。赤ちゃんなりの生活リズムが作られ、活発に動く時間と静かに過ごす時間の区別がつき始めるのです。
妊娠21週の赤ちゃんの様子
妊娠21週になると、赤ちゃんの骨格や筋肉がしっかりとしてきて、手でものを掴むことができるようになります。羊水の中を活発に動き回るようになり、お母さんはよりはっきりと胎動を感じられるようになるでしょう。
脳の発達も進み、脳の表面にシワができ始め、脳細胞が増加しています。これにより、脳の情報処理能力が高まっていきます。
また、皮膚の下に脂肪が蓄積され始め、赤ちゃんの体つきも少しずつ丸みを帯びてきます。赤ちゃんの体毛である産毛(うぶげ)も、全身を覆うようになります。
妊娠22週の赤ちゃんの様子
妊娠22週になると、赤ちゃんの眉毛やまつ毛が生え始め、顔立ちがはっきりしてきます。内臓や各器官もほぼ完成に近づき、機能的にも発達してきています。特に聴覚がさらに発達し、音の情報を脳に伝えられるようになります。
男の子の場合は、この頃から精巣からテストステロン(男性ホルモン)が分泌され始めます。また、妊娠22週は医学的には「生存可能な限界週数」とされており、万が一この時期に早産となった場合でも、高度な医療によって生存の可能性が出てくる時期です。
赤ちゃんの肺も発達を続け、肺胞と呼ばれる空気を取り込む小さな袋が形成され始めます。まだ完全ではありませんが、呼吸機能の基礎が作られている段階です。
妊娠23週の赤ちゃんの様子
妊娠23週になると、赤ちゃんの身長は約30cm、体重は約600g前後に成長します。髪の毛、まつ毛、眉毛がはっきりと生えてくるため、超音波検査でもより人間らしい姿が確認できるようになります。
それまで閉じていたまぶたも、この頃には上下に分離し、目を開けたり閉じたりすることができるようになります。筋肉や骨、内臓組織もさらに発達し、体の機能が向上していきます。
また、この時期になると赤ちゃんはママやパパの声を記憶し始めます。特にママの声や心拍は、常に聞こえているため、生まれた後もそれらの音に安心感を覚えるようになります。日常的に話しかけることで、赤ちゃんとの絆を深めることができるでしょう。
妊娠後期はいつから始まる?妊娠後期に避けた方がいいこととは?
妊娠6ヶ月に起きるママの変化は?
妊娠6ヶ月になると、ママの体にもさまざまな変化が現れます。お腹の張りや体調の変化など、気になる症状も増えてくる時期です。
どのような変化が起こるのか、そして体と心の状態をどのように管理すればよいのかを見ていきましょう。
妊娠6ヶ月の体型の変化と子宮の状態
妊娠6ヶ月になると、子宮底長(恥骨結合上縁から子宮底までの距離)が18〜21cmほどになり、おへその高さに達します。お腹が前方にせり出し、体の重心が変化するため、歩き方や姿勢も少しずつ変わってきます。
子宮の重みが増すことで、腰痛や背中の痛みを感じることが増えてきます。特に立ち仕事が多い方や、長時間同じ姿勢でいる方は注意が必要です。適度に休息を取りながら、無理のない範囲で活動するようにしましょう。
また、乳腺が発達し、乳首を押すと初乳(薄い黄色の乳汁)が出ることもあります。これは妊娠中から乳房が授乳の準備を始めている証拠で、正常な変化です。気になる場合は、健診時に医師に相談してみましょう。
妊娠6ヶ月に現れる身体の症状
妊娠6ヶ月頃には、さまざまな身体症状が現れることがあります。胸やけは、ホルモンの影響で胃の内容物と胃酸が逆流することで起こります。食事は少量ずつ、就寝前の食事は控えるなどの工夫が有効です。
背中の下部の痛みは、お腹の重みで姿勢が変化することによって起こります。骨盤をゆるめるホルモンの影響も加わり、腰回りに負担がかかりやすくなっています。適度なストレッチや温めることで和らげることができます。
ほてりは、ホルモン変化と新陳代謝の向上によるもので、多くの妊婦さんが経験します。涼しい服装を心がけたり、水分をこまめに摂ったりすることで対処できます。めまいは、血流の変化で上半身に血が届きにくくなることが原因です。急に立ち上がらないよう注意しましょう。
足のこむら返りは、特に夜間に起こりやすい症状です。カルシウムやマグネシウムの摂取、適度なストレッチが予防に効果的です。動悸や息切れは、心臓が妊娠前より50%多く血液を送り出していることによるもので、多くの場合は正常な変化です。しかし、激しい動悸や息切れが続く場合は医師に相談しましょう。
お腹の張りと対処法
妊娠6ヶ月になると、お腹の張りを感じることが増えてきます。これは子宮が大きくなり、時々収縮することによって起こります。
お腹の張りは一時的なものであれば心配ありませんが、強い痛みを伴ったり、規則的に起こったり、10分以内に何度も起こるようであれば、早産の兆候である可能性もあるため、すぐに医師に相談してください。
お腹の張りを感じたときは、横になって休んだり、温かい飲み物を飲んだり、トイレに行ったりすることで和らぐことがあります。
妊娠6ヶ月の健康的な過ごし方は?
妊娠6ヶ月は、赤ちゃんの急速な成長に伴い、「体重管理」と適切な「栄養摂取」が特に重要になる時期です。適切な体重増加は、健康な妊娠と出産のために欠かせません。ここでは、体重管理を行う際に注意すべきポイントと、必要な栄養素について解説します。

理想的な体重増加の目安
妊娠前のBMI(体格指数)によって適切な増加量は異なります。妊娠前のBMIが18.5未満のやせ型の方は12〜15kg、BMIが18.5〜25.0未満の普通型の方は10〜13kg、BMIが25.0~30.0未満の方は7~10kg、BMIが30.0以上の方は上限5kg(個別対応)が目安となります。
妊娠6ヶ月までの体重増加は、全体の約半分程度が目安です。つまり、妊娠全期で10kgの増加を目指す場合、妊娠6ヶ月終了時点では約5kg程度の増加が理想的です。過度な体重増加は妊娠高血圧症候群や巨大児出産のリスクを高める可能性があるため注意が必要です。
一方で、極端な食事制限は赤ちゃんの発育に影響を与える可能性があります。無理なダイエットは避け、バランスの良い食事を心がけましょう。体重の増加が気になる場合は、担当医に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。
バランスの良い食事のポイント
重要なのは食事の量ではなく、質の良い栄養バランスです。妊娠中期は特にタンパク質の摂取が重要になります。肉、魚、卵、豆腐などの良質なタンパク質を意識して摂るようにしましょう。
脂肪と糖分は控えめにし、間食を減らすことで過剰な体重増加を防ぐことができます。ただし、減食は禁物です。赤ちゃんへの栄養供給が最優先であり、必要なカロリーと栄養素はしっかりと摂取する必要があります。
また、鉄分、カルシウム、葉酸などのミネラルやビタミンも不足しがちです。緑黄色野菜、海藻類、乳製品などを積極的に取り入れましょう。食事だけでは補いきれない栄養素は、医師と相談の上、サプリメントを利用するのも一つの方法です。
水分摂取と便秘対策
妊娠中は血液量が増加するため、十分な水分摂取が必要です。1日あたり1.5〜2リットルの水分を摂ることを目標にしましょう。ただし、カフェインを含む飲み物や糖分の多い飲料は控えめにし、水や麦茶などを中心に摂るのが理想的です。
妊娠中は便秘になりやすく、特に妊娠6ヶ月頃からは子宮が大きくなり腸を圧迫するため、症状が悪化することがあります。便秘対策としては、食物繊維を多く含む食品(野菜、果物、全粒穀物など)を摂ることと、適度な運動が効果的です。
また、朝起きてすぐにコップ一杯の水を飲む習慣をつけると、腸の働きが活発になり便秘の予防になります。便秘がひどい場合は、自己判断で市販薬を服用せず、必ず担当医に相談してください。妊娠中に使用可能な便秘薬を処方してもらえます。
妊娠6ヶ月の不調対策|腰痛・むくみ・足のつりの改善方法
妊娠6ヶ月になると、つわりは落ち着いてくるものの、別のマイナートラブルが現れることがあります。これらの症状は多くの妊婦さんが経験する一般的なものですが、快適に過ごすためにはどのように対処すればよいのでしょうか。代表的なトラブルとその対処法を紹介します。

妊娠中の腰痛対策
妊娠6ヶ月になると、お腹の重みで姿勢が変わり、腰や背中に負担がかかります。正しい姿勢を意識し、長時間同じ姿勢でいることを避けましょう。
腰痛対策としては、骨盤ベルトや妊婦帯を適切に使用することで、骨盤を安定させ負担を軽減できます。また、腰や背中を温めることで血行が良くなり、痛みが和らぐこともあります。マタニティヨガやストレッチなど、妊婦向けの運動も効果的です。
仰向けに寝ると子宮が大血管を圧迫するため、左側を下にして横向きに寝るのがおすすめです。枕や抱き枕を使って、体を支えるようにすると楽に眠れることが多いです。痛みが強く日常生活に支障がある場合は、医師に相談しましょう。
妊娠中のむくみ解消法
妊娠中期から後期にかけて、特に足や手にむくみが現れることがあります。これは、子宮の圧迫で血液やリンパ液の流れが滞ることと、体内の水分量が増えることが主な原因です。軽度のむくみは正常な妊娠の変化ですが、急激なむくみや顔のむくみが見られる場合は要注意です。
むくみ対策としては、長時間同じ姿勢でいることを避け、足を少し高くして休むことが効果的です。また、きつい靴下や靴を避け、ゆったりとした服装を心がけましょう。適度な運動や、足首を回すなどの簡単なエクササイズも血行を促進します。
食事面では、塩分の摂りすぎに注意し、カリウムを多く含む食品(バナナ、アボカド、トマトなど)を取り入れるとよいでしょう。十分な水分摂取も大切ですが、一度にたくさん飲むのではなく、少量ずつこまめに飲むことがポイントです。
夜間の足のつり(こむら返り)対策
妊娠中期から後期にかけて、特に夜間に足がつる(こむら返り)ことがあります。これは、カルシウムやマグネシウムの不足、筋肉の疲労、血行不良などが原因と考えられています。突然激しい痛みに襲われることがありますが、多くの場合は一時的なものです。
この痛みへの予防策としては、カルシウムやマグネシウムを多く含む食品(乳製品、緑黄色野菜、ナッツ類など)を積極的に摂取することが大切です。また、就寝前に足をストレッチしたり、足の向きを変えながら寝たりすることも効果的です。
足がつってしまった場合は、足の指をゆっくり自分の方向に引き寄せ、ふくらはぎを伸ばすようにしましょう。また、つった部分をマッサージしたり、温めたりすることで痛みが和らぎます。症状が頻繁に起こる場合は、医師に相談し、薬の処方を検討してもらうとよいでしょう。
妊娠6ヶ月に行われる妊婦健診の特徴は?
妊娠6ヶ月の健診では、赤ちゃんの成長や母体の健康状態をより詳しく確認します。この時期特有の検査もあります。健診でどのようなことが行われ、何をチェックするのか理解しておくと安心です。
妊娠6ヶ月の超音波検査
妊娠6ヶ月の超音波検査では、胎児の成長指標として頭の横幅(BPD)、大腿骨の長さ(FL)、おなかの周囲の長さ(AC)、推定胎児体重(EFW)などが測定されます。これらの数値を妊娠週数ごとの標準値と比較し、赤ちゃんの発育状態を確認します。
また、この時期の超音波検査では、赤ちゃんの内臓や四肢の形態をより詳しく観察します。心臓の構造や機能、胃や腎臓、膀胱などの内臓の位置や形、手足の指の数なども確認されます。性別も確認できる時期ですが、希望しない場合は事前に伝えておきましょう。
羊水量も重要なチェックポイントです。羊水が多すぎたり少なすぎたりする場合は、何らかの問題がある可能性があります。また、胎盤の位置や状態も確認され、前置胎盤(子宮出口に胎盤がかかっている状態)などの異常がないかチェックされます。
ママの健康チェック項目|血圧・体重・尿検査で知る妊娠リスク
妊娠6ヶ月の健診では、ママの血圧、体重、尿検査が毎回行われます。血圧の上昇や尿蛋白の検出は、妊娠高血圧症候群の兆候である可能性があるため、慎重にチェックされます。体重増加も、適切な範囲内かどうか確認されます。
また、貧血の有無を確認するために、ヘモグロビン値や赤血球数などの血液検査が行われることもあります。妊娠中は血液が薄まり、貧血になりやすいため、定期的なチェックが必要です。貧血が見つかった場合は、鉄剤の処方や食事指導が行われます。
妊娠糖尿病スクリーニング検査
妊娠24週前後(妊娠6ヶ月頃)には、妊娠糖尿病のスクリーニング検査として糖負荷試験(50gGCT)が行われることがあります。この検査では、甘い飲料(ブドウ糖液)を飲んだ1時間後に血糖値を測定し、糖代謝の異常がないかを調べます。
50gGCTで陽性となった場合は、より詳細な75gOGTTを行います。検査前日から検査当日にかけて、食事制限や運動制限などの注意事項がある場合がありますので、医師の指示に従ってください。
妊娠糖尿病と診断された場合でも、適切な食事療法や運動療法、場合によってはインスリン療法を行うことで、母子ともに健康的に妊娠を継続することができます。定期的な血糖値のモニタリングと、医師の指示に従った管理が重要です。
妊娠6ヶ月からの出産準備ガイド
妊娠6ヶ月は、体調が比較的安定し、出産や育児に向けた準備を始めるのに適した時期です。赤ちゃんのための物品や環境の準備だけでなく、心と体の準備も大切です。この時期から始めておくとよい準備や心がけについて考えてみましょう。
出産に向けた体づくり
出産は体力を使うため、計画的に体力をつけておくことが大切です。この時期からマタニティヨガやマタニティスイミング、ウォーキングなど、妊婦に適した運動を習慣化するとよいでしょう。無理のない範囲で、定期的に体を動かすことを心がけましょう。
骨盤底筋のトレーニングも出産準備として効果的です。これは出産時の力みをサポートするだけでなく、産後の尿漏れ予防にも役立ちます。また、正しい呼吸法を練習しておくことも、分娩時に役立ちます。母親学級や両親学級で教わることが多いので、ぜひ参加してみましょう。
食事面では、バランスの良い食事を心がけ、特にタンパク質、鉄分、カルシウムなどの栄養素をしっかり摂取しましょう。良質なタンパク質は筋力維持に役立ち、鉄分は貧血予防、カルシウムは骨や歯の健康維持に重要です。
母親学級・両親学級への参加
多くの医療機関や自治体では、妊娠20週以降の妊婦さんとそのパートナーを対象に、母親学級や両親学級を開催しています。これらの教室では、妊娠中の過ごし方、出産の流れ、呼吸法、赤ちゃんのお世話の仕方などを学ぶことができます。
特に初めての出産では不安なことも多いため、専門家から正しい知識を得ることは非常に重要です。また、同じ時期に出産を控えている仲間と知り合う機会にもなり、情報交換や精神的なサポートを得ることができます。
パートナーと一緒に参加することで、二人で協力して出産・育児に臨む意識が高まります。赤ちゃんのお風呂の入れ方や、おむつの替え方などの実践的な練習ができる教室もあります。出産を控えたパパにとっても、貴重な学びの場となるでしょう。
赤ちゃんとのコミュニケーション
妊娠6ヶ月になると、赤ちゃんはママやパパの声を聞き分けられるようになります。この時期から積極的に話しかけることで、赤ちゃんとの絆を深めることができます。お腹の赤ちゃんに日常の出来事を話したり、歌を歌ったりすることは、胎教としても効果的です。
また、お腹をやさしくなでることで、赤ちゃんが反応して動くことがあります。このような触れ合いも、赤ちゃんとのコミュニケーションの一つです。パパにもお腹に手を当ててもらい、赤ちゃんの存在を実感してもらうとよいでしょう。
胎動を感じたら、「元気にしてるね」「ありがとう」など、返事をするように話しかけると、自然とコミュニケーションが生まれます。生まれる前から親子の絆を育むことは、産後の育児にもプラスに働くでしょう。心と心のつながりを大切にしながら、残りの妊娠期間を過ごしましょう。
妊娠6ヶ月に気をつけるべき注意サイン
妊娠6ヶ月は比較的安定した時期ですが、いくつか注意すべき症状があります。これらの症状が現れた場合は、早めに医療機関を受診することが大切です。妊娠中の異常を早期に発見し、適切な対応をとるために、注意すべきサインについて理解しておきましょう。
早産の兆候と対応
妊娠6ヶ月は、まだ赤ちゃんが十分成熟していない時期です。この時期に早産の兆候が現れた場合は、すぐに医療機関を受診する必要があります。早産の主な兆候としては、規則的な子宮収縮(10分以内に繰り返す腹部の張り)、腰の痛みを伴う下腹部痛、腟からの出血、破水(腟からの水様の液体の流出)などがあります。
特に子宮収縮が規則的になったり、頻度が増したりする場合は要注意です。安静にしても収まらない場合や、痛みを伴う場合は、すぐに医師に連絡しましょう。早期に対応することで、早産を防げる可能性があります。
日常生活では、過度な運動や長時間の立ち仕事、重い物の持ち上げなどを避け、適度な休息を取ることが大切です。
妊娠高血圧症候群の兆候と対応
妊娠高血圧症候群(かつての妊娠中毒症)は、高血圧が現れ、タンパク尿を伴うこともある合併症です。この症状が進行すると、母子ともに危険な状態になる可能性があるため、早期発見が重要です。
妊娠高血圧症候群の主な兆候としては、急激な体重増加(1週間で1kg以上)、手や足の著しいむくみ、顔面特に目の周りのむくみ、頭痛、目の症状(かすみ目やチカチカする)、上腹部痛などがあります。これらの症状が現れた場合は、すぐに医療機関を受診してください。
予防策としては、適切な体重管理、バランスの良い食事(特に塩分控えめ)、適度な運動、十分な休息などが挙げられます。また、定期的な健診を欠かさず、血圧や尿検査の異常を早期に発見することも重要です。
胎動減少時の対応
妊娠6ヶ月になると胎動を明確に感じられるようになりますが、胎動が急に減少したり、長時間感じられなくなったりした場合は注意が必要です。胎動の減少は、赤ちゃんの状態に変化が生じている可能性があります。
胎動が心配な場合は、左側を下にして横になり、意識して胎動をカウントしてみましょう。普段と比べて明らかに少ない場合は、医療機関に連絡することをおすすめします。
胎動カウントは、毎日同じ時間帯(赤ちゃんが活発に動く時間)に行うと良いでしょう。また、空腹時や食後、甘いものを摂取した後などは胎動が活発になりやすいという特徴があります。日頃から赤ちゃんの動きのパターンを把握しておくことで、異変に気づきやすくなります。
妊娠6ヶ月に関するよくある質問
妊娠6ヶ月(20〜23週)は体調が安定してくる一方で、新たな変化や疑問も生まれる時期です。ここでは、多くのママから寄せられる疑問について、専門家の視点からわかりやすく解説します。
Q .妊娠6ヶ月のお腹の大きさや体重増加の目安はどれくらいでしょうか?
A .体重増加の目安は、妊娠前のBMIによって異なりますが、妊娠6ヶ月終了時点で約5kg程度の増加が一般的です。
ただし、体重増加のパターンは個人によって異なります。つわりがひどかった方は、妊娠初期に体重が減少し、中期以降に急に増えることもあります。定期健診で医師から特に指摘がなければ、過度に心配する必要はありません。
Q .妊娠6ヶ月で逆子と言われた場合、自然に戻る可能性はありますか?
A .妊娠6ヶ月で逆子(骨盤位)と診断されても、心配する必要はありません。この時期はまだ赤ちゃんが小さく、羊水の中で自由に動けるため、頭位(頭が下になる正常な状態)と骨盤位を何度も繰り返すことが一般的です。
妊娠32週頃までは、ほとんどの赤ちゃんが自然に頭位に戻ります。妊娠後期になっても逆子が続く場合は、医師が外回転術(お腹の上から手で赤ちゃんの向きを変える処置)を行ったり、逆子体操を勧めたりすることがあります。
Q .妊娠6ヶ月に適した運動や体づくりについて知りたいです。
A .妊娠6ヶ月は、体調が比較的安定している時期なので、適度な運動を取り入れるのに適しています。ウォーキングは最もおすすめの運動で、20〜30分程度、週3〜4回行うとよいでしょう。急な坂道や長時間の運動は避け、疲れを感じたらすぐに休憩してください。
骨盤底筋のトレーニングも出産準備として重要です。腟や肛門を締めるように意識し、5秒間キープする運動を1日10回程度行うとよいでしょう。また、四つん這いの姿勢から猫のようにお尻を上げ下げする「猫のポーズ」は、腰痛予防や赤ちゃんの位置を整えるのに役立ちます。いずれの運動も、医師に相談してから始めることをおすすめします。
【妊娠6ヶ月まとめ】安定期を健やかに過ごすための重要ポイント
妊娠6ヶ月(20〜23週)は、安定期の真っただ中であり、赤ちゃんの成長が目覚ましい時期です。赤ちゃんは超音波検査ではっきりとした姿が確認でき、内臓や骨格が発達し、ママの声を聞き分けられるようになります。
ママの体もさまざまな変化が現れ、お腹の張り、腰痛、むくみなどのマイナートラブルに直面することがあります。適切な体重管理とバランスの良い栄養摂取、適度な運動で、これらの症状を和らげることができます。
また、この時期は出産に向けた準備を始めるのに適しています赤ちゃんとのコミュニケーション、出産に向けた体づくりなど、心と体の準備を進めましょう。
妊娠6ヶ月は、赤ちゃんとの絆を深め、出産に向けて前向きに準備を進める大切な時期です。体調の変化に敏感になりながらも、この特別な時間を楽しんで過ごしましょう。
不安なことがあれば、担当医や助産師に相談してください。安心して妊娠生活を送ることが、ママと赤ちゃん双方の健康につながります。




