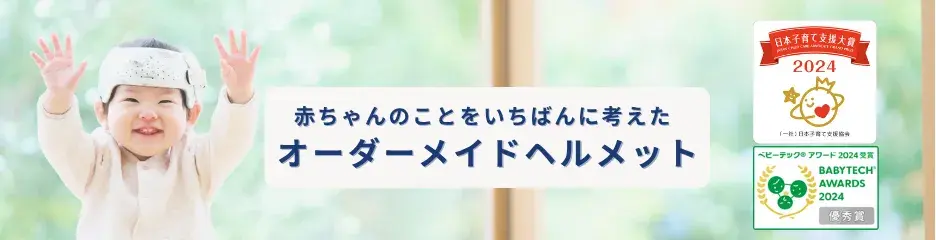公開日2025年11月25日
東京都練馬区の赤ちゃんの頭の形を相談できる外来|順天堂大学医学部附属練馬病院
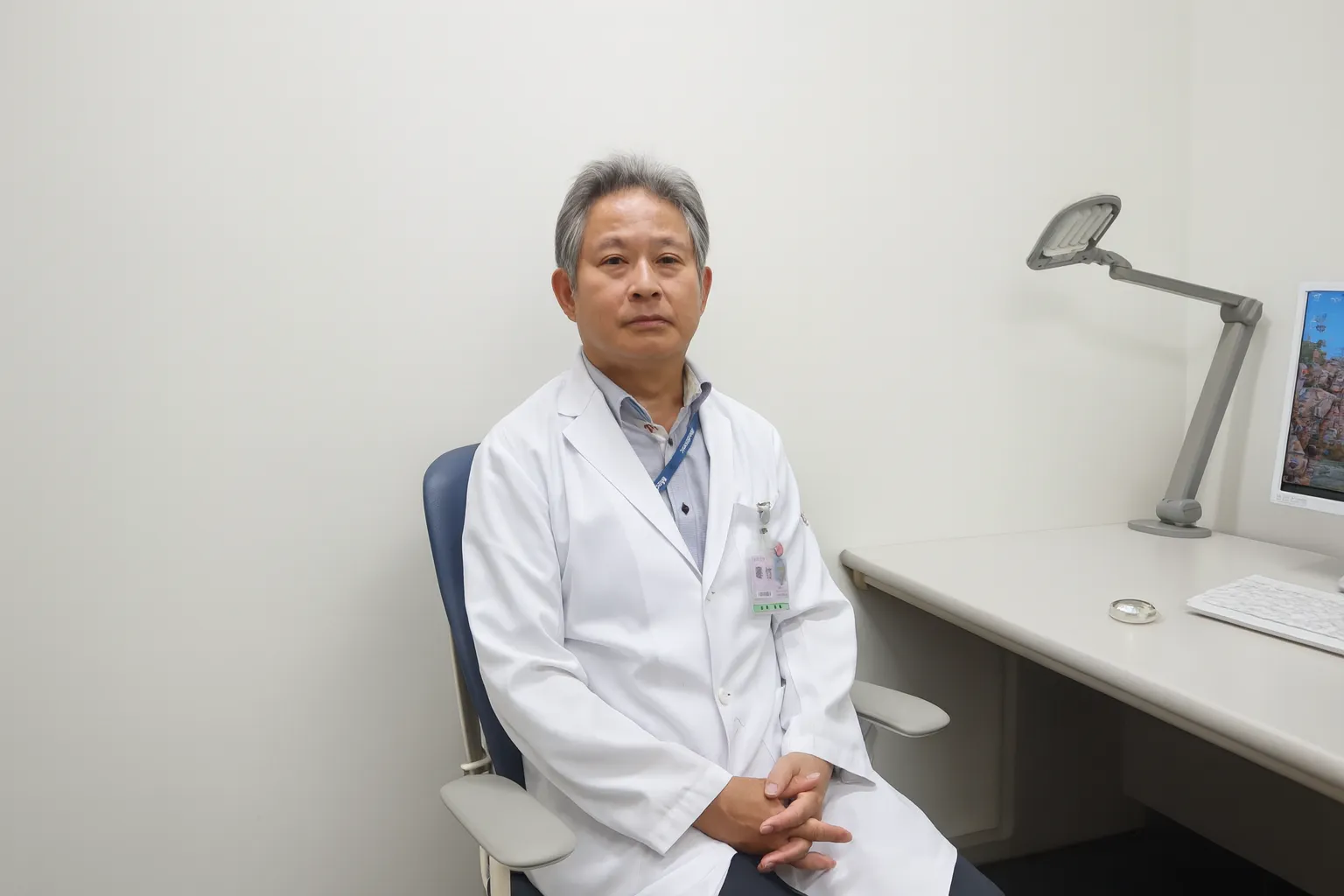
この記事では、先生が日々の診療で大切にしている考え方を中心にご紹介します。
赤ちゃんの頭の形やヘルメット治療に関する基本的な情報は、別記事でご覧いただけます。
先生のご経歴を教えていただけますか
1988年に千葉大学医学部を卒業し、卒業後は大学院に進みました。当時は分子生物学や遺伝子の研究に強い関心があり、4年間免疫の研究に取り組みました。研究職の道もありましたが、臨床への思いが強 かったことに加え、発生学への興味から小児科を選択しました。特に松戸市立病院1988年に千葉大学医学部を卒業し、卒業後は大学院に進みました。当時は分子生物学や遺伝子の研究に強い関心があり、4年間免疫の研究に取り組みました。研究職の道もありましたが、臨床への思いが強かったことに加え、発生学への興味から小児科を選択しました。 千葉大学小児科に入局後、成田赤十字病院や松戸市新生児科での経験は大きく、6年間にわたって新生児医療に携わりました。2000年に順天堂大学に移り、順天堂大学医学部附属浦安病院で新生児センターの立ち上げに尽力しました。当時、新生児医療の体制が整っていなかった同病院で、経営層へのアピールから人材確保、実績づくりまで行い、10年かけて地域周産期センターの認可を取得しました。 2014年に順天堂大学医学部附属静岡病院に赴任し、約8年半を過ごしました。静岡病院では臨床業務に加えて、災害医学研究センターの設立により、長年やりたかった分子生物学の研究環境が整い、実験助手のサポートを得ながら研究活動にも注力できました。この時期に多くの論文を執筆し、現在の基盤を築くことができました。そして2020年頃、練馬病院の新生児センター立ち上げの依頼を受け、現職に至ります。3年前から教授として、新生児科の診療責任者および小児周産期センターの責任者を務めています。
医師を目指したきっかけはありますか
医師を目指したのは父親の影響が大きかったです。父は歯科医で、兄がその跡を継ぎ、次男の私は幼い頃から父に医者になるようにと言われ続けてきました。正直に言うと、医師が天職とは思っていないんです。他の職業はどうだっただろうかと今でも考えることがあります。実は学校の教師にも憧れがあったんです。子供と接することが好きだったことから小児科を選びました。臨床医としてのやりがいを感じつつも、医療は患者を健康な状態に戻すのが仕事で、ゴールが決まっています。その中でクリエイティブな仕事にも興味があったため、研究活動にも力を入れてきました。
練馬病院の特徴を教えてください
練馬病院の大きな強みは、診療科間の良好な連携にあります。特に産婦人科、新生児科、小児科、小児外科の四科で構成される小児周産期センターでは、各科の都合ではなく「子供ファースト」で治療方針を決定しています。各科が「うちの手術日は月曜日だから」「火曜日しか無理」などと自科の都合を主張しがちですが、練馬病院ではそういうことはあまり言いません。子供に合わせて手術予定を柔軟に調整するなど、お互いに歩み寄る姿勢があります。 産婦人科のカンファレンスに小児科も参加し、胎内にいる段階から外科疾患の可能性などを話し合い、出生のタイミングや手術の予定を子供の状態に合わせて決めています。こうした横の連携が優れていると思 います。
どんな診療を心がけていますか
診察で心がけているのは、意外かもしれませんが「むやみに目を合わせないこと」です。凝視すると怖がる子供が多いため、視線をパソコンや母親に向けながら、さりげなく子供を観察するようにしています。お子さんとは、特別に意識しなくても自然に接することができていると思います。
頭のかたち診療を始めたきっかけを教えてください
頭のかたちについて詳しい先生の話を何度か聞いたことがあり、以前から関心を持っていました。頭のかたち外来の開設前は、頭の形の診療をしている病院に紹介したこともあります。始めたきっかけは自院でフォローしていた双子の患者さんからヘルメット治療の相談を受けたことでした。その子たちは早産で生まれ、数年にわたってフォローする予定の子供たちでした。自分がずっと診ていく患者さんからのニーズがあったことが、外来を始める大きな理由になりました。実は頭のかたちの相談は以前から多く、地域のニーズは確実にあると感じていました。
診療の流れを教えてください
現在は月曜日午後のフォローアップ外来の枠内で実施しています。初診では3Dカメラ撮影、ノギス計測、データ送信などの作業があり、30分程度かかります。その後は月1回程度の通院で、治療期間は約4ヶ月が目安です。
読者の方へのメッセージをお願いします
頭の形は将来本人も気になることがありますし、首がすわった頃から開始できるため、気になるのであれば 早いうちに相談いただけると良いと思います。頭のかたち以外でも子育てに関する相談を受け付けているため、私たちのサポートが少しでもご家族やお子さんの力になれたら、と思っています。
ヘルメット治療について
治療の流れ
初診は3Dカメラ撮影、ノギス計測、データ送信などの作業があり、30分程度かかります
費用
33万円(税込)
診察日時
月曜日 午後
予約
電話にて予約を受け付けております
相談窓口

アクセス
電車・バスでお越しの方: 西武池袋線 練馬高野台駅下車徒歩6分
お車でお越しの方: 関越自動車道練馬インターから約10分